岸本佐知子さんの「トーク&サイン会」平安堂長野店
『気になる部分』岸本佐知子(白水 Uブックス)\920+ 税 2006/06/28
●『フェルマータ』ニコルソン・ベイカー(白水社)という、へんてこりんな小説を読んだのは富士見に住んでいた頃だったか。主人公の男が「時間よ止まれ!」パチンと指を鳴らせば、周囲の世界は一瞬にして固まってしまう。その中を彼一人だけが動き回れるのだ。さて、彼はいったいどういう行動をとったのか? 透明人間の話とちょっと似ているがぜんぜん違う。この本の訳者が、岸本佐知子さんだった。
変な小説を好んで訳す、岸本佐知子さんも相当に「変な人」だ。彼女のエッセイ集『気になる部分』を読んでたまげてしまった。これは久々にホームランだ。大笑いしたあと、しみじみ懐かしくなって、読んでいるうちに次第に現実感覚が崩壊してきて、夢ともうつつともつかない奇妙な宙ぶらりんな感覚にもってゆかれるのだ。いや本当に凄い書き手だね。もっともっと読んでみたいぞ。
笑った話は、「私の健康法」の中の数々の「ひがみネタ」。<飲食店で邪険にされた思い出> <自分だけ仲間はずれにされた> <旅先でボラれた> <自分の並ぶ列が必ず一番遅い>など、その時の気分に応じて好みのネタをセレクトし、心ゆくまでひがみエクスタシーを味わったあと、すっきりした気分で安眠するのだという。変な人だね(^^;) 「ラプンツェル未遂事件」も笑った。これは脚色はないんだろうな、きっと。
彼女が某洋酒メーカー(ぼくが想像するに、サントリーではないかと思うのだが)の宣伝部に勤めていたころの話も抱腹絶倒だ。中でも傑作なのが、「国際きのこ会館」の思ひ出 だ。全て本当の話なんだろうが、語り口がシュールなのね。ぼくは、筒井康隆の傑作短編『熊の木本線』の、あの不気味な雰囲気を思い出した。終いまで読んだら、彼女はどうも相当な筒井フリークであるらしい。やっぱしな(^^;)
「寅」の、”流しの OL”もよかったな。あと、個人的に大笑いしたのは、「じっけんアワー」の懐中電灯で月を照らしてみて、しかし、どんなに目を凝らしても、月の私が照らしているあたりが明るくなったようには見えなかった、という子供の頃の話と、「真のエバーグリーン」の中の、『秋元むき玉子』の話だ。ぼくも、「秘本むき玉子」とかいうタイトルを高校生の頃見て、ドキドキしたことがある。エッセイ中には「腰元むき玉子」という映画があったとあるが、これは絶対『秘本むき玉子』(1975年、日活ロマンポルノ)のことだと思うぞ。
■しかし、このエッセイ集の中で一番に読み応えがあるのは、彼女の子供の頃の話だ。「気になる部分」の新幹線の一番前の、あの丸い部分。よく泊まりにいった祖母の家の枕に住んでいた「日本兵」の行軍のはなし。「カノッサの屈辱」という、彼女が通ったカノッサ幼稚園の思い出。あと、すごく好きなのが「石のありか」と、それに続く「夜の森の親切な小人」「夜になると鶏は……」(これって、サイモンとガーファンクルの曲「四月になれば彼女は」なんだろうね)「サルの不安」、そうして「トモダチ」だ。 この路線が、彼女には一番合っていると思う。
ここを読んで思い浮かべるのは、『人形の旅立ち』長谷川摂子(福音館書店)や、内田百けん『冥途』だ。夢か現(うつつ)か、知らないうちに読者の足下をすくわれるような現実崩壊感を、ぼくらは読みながら味わうことになるのだ。現実と虚構の境目なんて、じつはないんだよね! 岸本佐知子さんには、ぜひ小説を書いて欲しいように思うのは、ぼくだけだろうか?
http://media.excite.co.jp/book/special/honyaku/index.html
http://www.fellow-academy.com/fellow/magazine/userMailMagazineView.do?deliveryId=4
それから、『本の雑誌』2005年11月号で、大森望氏、トヨザキ社長との鼎談が笑わせる「フラメンコ書評」の話が楽しかったな。
あと、2002年から2004年にかけて、『母の友』(福音館書店)誌上で、彼女は隔月で書評を書いていて、ぼくはずっと読んできたはずなのに、あまり印象がなかった。で、書庫にとってある『母の友』を探してきて、片っ端から確かめて読んでみたのだが、予想に反して、岸本佐知子さんが好む本の嗜好性と、ぼくの嗜好性とは、ほとんど相容れないことに気が付いた。淋しかった。でもまぁ、彼女が書く文章を読んでいるだけで、幸せになれるんだから、それでもいいか(^^;;) (2006/ 7/14)
『ねにもつタイプ』岸本佐知子(筑摩書房) 2007/03/23
■2月初めに本やCDをまとめて Amazon に注文したら、いつまでたってもちっとも発送されて来ない。例の村上春樹氏推薦のシダー・ウォルトン(p)トリオのCD『ピットイン』が入手困難となったためで、結局、それ以外の注文品が今週の火曜日になってようやく届いた。その中の一冊に『ねにもつタイプ』岸本佐知子(筑摩書房)があった。一字一句ねめるように味わいつつ、ページが進むのを惜しみつつ、でも止められない止まらない「かっぱえびせん」状態になってしまい、あっと言う間に読了してしまった。あぁ面白かった(^^)
■以下の文章は『考える人』に載ったエッセイからの引用で、本書『ねにもつタイプ』からのものではないのだが(同じネタの文章はある)こちらの方が「岸本佐知子らしさ」がよく出ていると思うので、以下引用。
今日も幼稚園で泣いた。お弁当を食べるのがビリだったせいだ。きのうもおとといも泣いた。入園してから泣かなかった日が三個ぐらいしかない。幼稚園なんてなくなればいいのにと思う。
家に帰ると、たいてい近所のSちゃんの家で遊ぶ。行くと必ずお人形遊びをさせられる。Sちゃんがバービーを手に持って、変な高い声で「お買い物に行きましょう」とか言う。そしたらこっちもタミーの声で「そうしましょう」とか言わないといけない。(中略)お人形遊びなんかやりたくない。でもそのことは、なぜだか絶対に言っちゃいけないような気がする。ばれちゃうから。ばれるって何が? わからない。地球人のふりをして生きてる宇宙人も、こんな気持ちかもしれない。
Sちゃんちで出されるのはいつもカルピスで、飲むと喉の奥に変なモロモロが出る。そのモロモロを口の中で持て余しながら、あーあ、早く大人になりたいな、とか思っている私は、大人には大人の幼稚園やお人形遊びがあることも、「地球人のふりをしている宇宙人の気持ち」が、その後の人生でずっとついて回ることも、この時はまだ知らない。(『カルピスのモロモロ』より)『考える人』季刊誌2004年秋号(57ページ「子どもをめぐる八つのおはなし」より)。
それにしても、よくもまぁ手を替え品を替え、決して読者をワンパターンで飽きさせないような文章を次から次へと紡ぎ出すものだ。全てのパートが甲乙付けがたい傑作だと思う。ぼくも「マイ富士山」が欲しいぞ。
■それから、ビックリしたのが「くだ」(p49)の冒頭部分だ。(以下引用)
小学三年生の冬、鰻のあとにプリンを食べたらお腹が痛くなった。いつまでも治らないので、盲腸ではないかと大人たちが言いだした。盲腸なら手術だ。手術は嫌だ。だから「もう痛くない」と嘘をつき、そのまま年を越した。そのうちとうとう歩けなくなって嘘がばれ、病院に担ぎ込まれて即入院、手術の運びとなった。
でも、触診でお腹を押すと、どうも痛がり方が尋常ではない。「本当にここが痛いの?」と左下腹部を押すと、彼女はちょっとだけ痛そうな顔をして「うん」とスマして答える。これはよく言われていることだが、急性虫垂炎の患者さんは診察室に入ってくるところを見れば判ると、よく言われる。いかにも痛そうに右下腹部を右手で押さえながら、前屈みになって足を引きずるようにして入って来るからだ。ところが、Rちゃんは背筋を伸ばして普通に歩いてきた。試しにその場でジャンプさせてみたが、平気で10回くらい「その場飛び」をして見せてくれた。
それでも、ぼくは気になったので血液検査をしてみたら、白血球増多とCRP↑の所見があったので、伊那中央病院救急センターに「急性腹症の疑い」で紹介することにしたのだ。
その次の日のお昼に、彼女のお母さんから電話が入った。ちょうど彼女のお兄さんが小学3年生だった時に急性虫垂炎になって緊急手術をしていて、その時の記憶が「ものすごい恐怖=手術は怖い!」となって彼女の心に刻まれたのだという。だから、お腹が痛い→急性虫垂炎→手術 という公式が彼女の中で出来上がっていて、怖ろしい手術だけは絶対にイヤだったから、本当は右下腹部が「ものすごく痛かった」のに左下腹部が痛いと嘘を言ったのだという。結局、彼女は本当に急性虫垂炎で、その日の深夜、緊急手術が実施され間一髪で破裂前(腹膜炎前)の虫垂は切除されたのだった。
虫垂は破裂していなかったけれども、腹水が大量に貯まっており、用心のためドレナージの「くだ」が彼女のお腹にも立ったという。幸い腹膜炎は起こしておらず、3月18日に無事退院できたそうだ。いやはや驚いた。ものすごく痛かったであろうに、ぼくの前で平気な顔をして10数回ジャンプして見せてくれたのだよ! 信じられないな、こどもって(^^;;
ビックリしたと言えば、「あとがき」に「べぼや橋」の検索ヒット数は一件から三件に増えた と書かれていたので、試しに「べぼや橋」をググってみたら16200件もヒットして驚いた。岸本佐知子って、知らないうちにこんなにもメジャーになっていたのか!と驚嘆した。しかしよく見ると、実際の「べぼや橋」は8件のみで、あとは「ぼや」にヒットしたものだった。なぁんだ。
ちなみに、「秋元むき玉子」で検索すると、ぼくの「しろくま」のファイルの「2006/06/28の日記」1件しかヒットしない。いやはや(^^;;
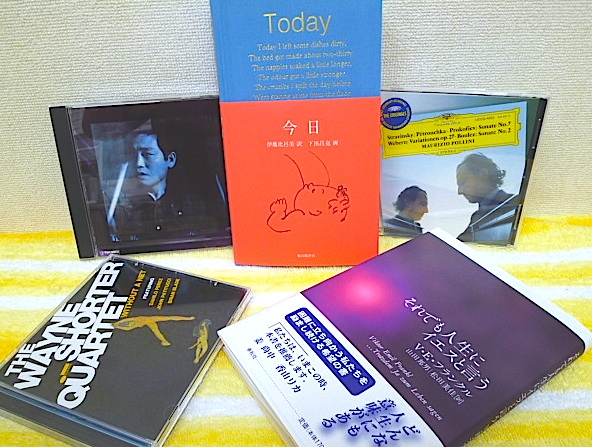


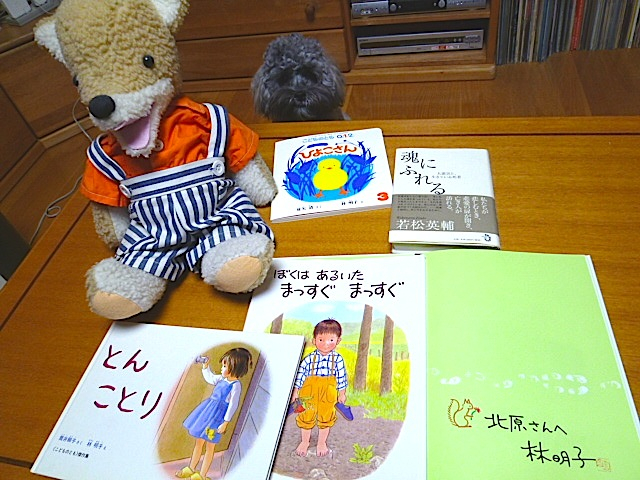
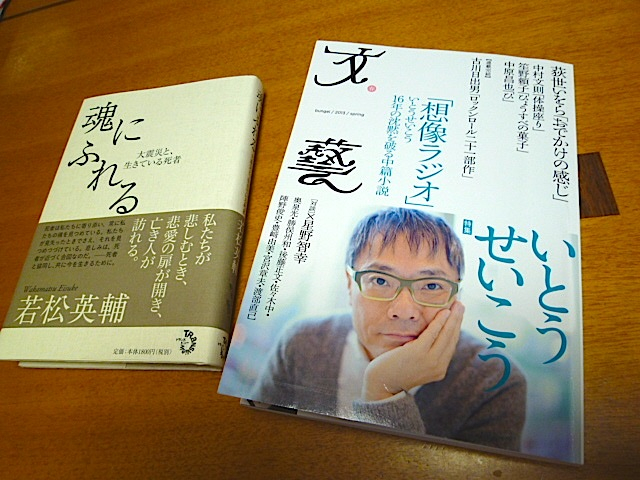



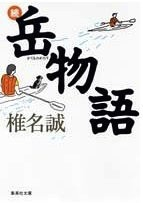
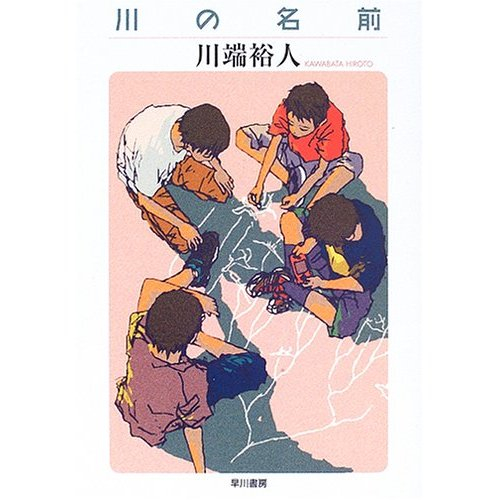
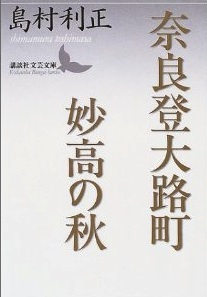 いま、ふと思い出した「父と息子」の短篇小説がありました。それは、昨年生誕
いま、ふと思い出した「父と息子」の短篇小説がありました。それは、昨年生誕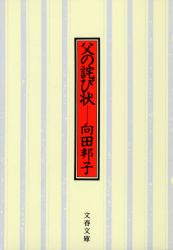 小説ではありませんが、向田邦子『父の詫び状』(文春文庫)を読むと、明治生まれの頑固な父親像が、娘の目を通して様々なエピソードと共に印象的に描かれていて実に読み応えがあります。向田さんの文章は、読んでいて読者の五感に直接訴えてきます。食べ物の美味しそうなにおい、写真館で担任の先生の手が彼女の肩に触れた感触など、視覚聴覚以外の感覚(嗅覚、触覚、味覚など)もリアルに刺激されるのです。
小説ではありませんが、向田邦子『父の詫び状』(文春文庫)を読むと、明治生まれの頑固な父親像が、娘の目を通して様々なエピソードと共に印象的に描かれていて実に読み応えがあります。向田さんの文章は、読んでいて読者の五感に直接訴えてきます。食べ物の美味しそうなにおい、写真館で担任の先生の手が彼女の肩に触れた感触など、視覚聴覚以外の感覚(嗅覚、触覚、味覚など)もリアルに刺激されるのです。
最近のコメント