『想像ラジオ』いとうせいこう著(河出書房新社)
上伊那医師会 北原文徳
もし本屋さんで「この本」を見かけたなら、試しにちょっと本のカバーを外してみて欲しい。真っ白いシンプルな表紙の左上に、ただ小さくこう書かれているはずだ。
想ー像ーラジオー。
ラジオの深夜放送で、CMブレイクの前後に流されるジングル。「オールナイト・ニッポン」とか「パック・イン・ミュージック、TBS」とかね、懐かしいあの音。
70年代〜80年代にかけて、ラジオの深夜放送が僕の心の友だった。帰宅後夕飯を食べたら、まずはすぐに寝る。夜11時に起こしてもらって、それからが勉強だ。夜中ひとりで起きていると、怖いし淋しい。だからラジオをつける。すると、DJが明るい声で僕のために語りかけてくれるのだ。「淋しいのは君だけじゃないよ!」ってね。
高校2年生の春、TBSラジオの「林美雄パック」に投稿して採用され、TBSのネーム入りライターを貰った。自慢しようと学校へ持って行ったら、現国の伊藤先生に見つかって取り上げられてしまった。高校生にライターを景品に贈るというアバウトさ。今なら考えられないことだ。
林美雄アナウンサーは、伝説のサブカル・カリスマ・リーダーだった。僕がまだ中坊だった頃、深夜のスタジオで荒井由実が『ベルベット・イースター』をピアノで弾き語りした。石川セリの『八月の濡れた砂』を聴いたのも、タモリの「4カ国親善麻雀」を初めて聴いたのも、原田芳雄と松田優作が『リンゴ追分』を生デュエットしたのも、すべて「林美雄ミドリブタ・パック」だった。
林アナが「これを聴け!」とプッシュしたミュージシャンは、まず間違いがなかった。佐野元春、山崎ハコ、上田正樹。みんな彼に教わった。それに、映画『青春の蹉跌』と『フォロー・ミー』もね。当時の深夜放送DJは、ラジオリスナーに対して絶対的な影響力があったのだ。
ところで、この『想像ラジオ』は深夜午前2時46分から明け方まで毎晩放送されている。
こんばんは。
あるいはおはよう。
もしくはこんにちは。
想像ラジオです。
と、軽快に語り始めるのはDJアークだ。ただこの想像ラジオ、スポンサーはないし、ラジオ局もスタジオも電波塔もマイクすらもない。昼夜を問わず、リスナーの「想像力」の中だけでオンエアされているという特殊な番組なのだ。
まるで、三代目春風亭柳好の落語「野ざらし」を聴いているみたいな歌い調子で小気味よく、軽やかに語りかけてくるDJアークは38歳。年上の妻と中2の息子が一人いる。音楽業界の仕事に疲れ郷里に戻り、海沿いの小さな町で心機一転頑張ろうとした矢先に記憶が途切れ、気が付いたら、高い杉の木のてっぺんに引っかかって、赤いヤッケを着たまま仰向けになっていた。その状態でラジオ放送を続けているという何とも不条理な状況設定。
しかし、読んでいて不思議とリアリティがある。DJアークの声も、彼がかける曲も実際に聞こえてくるようだ。番組最初の1曲は、モンキーズの『デイドリーム・ビリーバー』。リスナーによっては、忌野清志郎の日本語バージョンでオンエアされる。想像ラジオだからね。4曲目は、ボサノバの巨匠アントニオ・カルロス・ジョビンで『三月の水』。ブラジルの歌姫エリス・レジーナとジョビン本人がデュエットしているCDは僕も持っている。二人の寛いだ雰囲気が何とも楽しい曲だ。

DJアークのもとには、放送を聴いたリスナーから次々とメールやお便りが寄せられる。直接電話してくる人もいる。ただ、誰もが「この放送」を聴ける訳ではない。例えば、いとうせいこう氏本人を思わせる「私」には聴こえない。DJアークの妻と息子にも、この放送は届いていないらしい。
5曲目、ジョビンの熱烈なファンであり『アントニオの歌』のヒットで知られるマイケル・フランクスが、ジョビンの死を悼んで作った『アバンダンド・ガーデン(打ち棄てられた庭)』。そして6曲目が『あの日の海』コリーヌ・ベイリー・レイ。この曲は知らなかったが、松本の中古CD店で見つけて買って帰った。静かで優しい曲調の歌だったが、最後のフレーズの訳詩を見て驚いた。
海よ
荘厳な海よ、あなたは
全てを壊し
全てを砕き
全てを洗い浄め
私の全てを
呑み込んでくれるのね
そう、想像ラジオで流される曲は、あの事実と密接にリンクしていたのだ。2時46分、三月の水、打ち棄てられた庭、そして、あの日の海。ということは、このラジオのリスナーたちはみな、「あの日」に亡くなった死者たちなのか? じゃぁ、DJアークも? 死者たちの声は、生き残った者たちの耳には聴こえないのか? それこそが、この小説のテーマだ。
3.11 以降「当事者」でない者が、安全地帯に居ながら偉そうに語ることは不謹慎だとさんざん言われてきた。著者は、それを十分承知の上で「第二章」「第四章」で持論を述べる。ここは読み応えがあった。以下は「私」たちがボランティア活動を終え、被災地から帰る深夜の車中での会話。
「俺もあくまで相手のためみたいな顔で同情してみせて、ほんとはなんていうか、他人の不幸を妄想の刺激剤にして、しかもその妄想にふけることで鎮魂してみせた気分になって満足するだとしたら、それは他人を自分のために利用していると思う。(中略)だけどだよ、心の奥でならどうか。てか、行動と同時にひそかに心の底の方で、亡くなった人の悔しさや恐ろしさや心残りやらに耳を傾けようとしないならば、ウチらの行動はうすっぺらいもんになってしまうんじゃないか。」
「いくら耳を傾けようとしたって。溺れて水に巻かれて胸をかきむしって海水を飲んで亡くなった人の苦しみは絶対に絶対に、生きている僕らに理解できない。聴こえるなんて考えるのはとんでもない思い上がりだし、何か聴こえたところで生きる望みを失う瞬間の本当の恐ろしさ、悲しさなんか絶対にわかるわけがない」(p69〜p72)
さらに第四章で交わされる、かつての不倫相手と「私」との会話。
「実際に聴こえてくるのは陽気さを装った言葉ばっかりだよ。テレビからもラジオからも新聞からも、街の中からも。死者を弔って遠ざけてそれを猛スピードで忘れようとしているし、そのやりかたが社会を前進させる唯一の道みたいになってる」(中略)「死者と共にこの国を作り直して行くしかないのに、まるで何もなかったように事態にフタをしていく僕らはなんなんだ。この国はどうなっちゃったんだ」(中略)「亡くなった人はこの世にいない。すぐに忘れて自分の人生を生きるべきだ。まったくそうだ。いつまでもとらわれていたら生き残った人の時間も奪われてしまう。でも、本当にそれだけが正しい道だろうか。亡くなった人の声に時間をかけて耳を傾けて悲しんで悼んで、同時に少しずつ前に歩くんじゃないのか。死者と共に」(p124〜p133)
この「第四章」のリアリティを理解するのはちょっと難しい。こうして「生者」のそばにいる「死者」は、幽霊でもオカルトでもスピリチュアルでもなく、でも確かに実在する存在なのだ。そのあたりのことは、気鋭の哲学者、若松英輔氏の著書『魂にふれる 大震災と生きている死者』(トランスビュー)を読むと少し分かってくる。
柳田國男は、ある日「あとは先祖になるのです」と話す初老の男性に出会う。幸せな人生を生きることができたのは、自分とその家族の毎日を守護する「先祖」のお陰であり、死者となってからは、今度は自分もその一翼を担いたいと言うのだ。
「死者は遠くへはいかない。愛する人のもとに留まる。また『顕幽二界』、すなわちこの世とあの世の往き来はしばしば行われる。祭りは、もともと死者と生者が協同する営みだが、死者の来訪は春秋の祭りに限定されない。また、生者と死者が互いに相手を思えば、その心はかならず伝わる。」(『魂にふれる』p130) 古来日本人はみな、そう信じてきたのではなかったか。さらに若松氏は言う。
「死を経験した人はいない。しかし、文学、哲学、あるいは宗教が死を語る。一方、死者を知る者は無数にいるだろう。人は、語らずとも内心で死者と言葉を交わした経験を持つ。だが、死者を語る者は少なく、宗教者ですら事情は大きくは変わらない。死者を感じる人がいても、それを受けとめる者がいなければ、人はいつの間にか、自分の経験を疑い始める。ここでの『死者』とは、生者の記憶の中に生きる残像ではない。私たちの五感に感じる世界の彼方に実在する者、『生ける死者』である。(中略)
死者が接近するとき、私たちの魂は悲しみにふるえる。悲しみは、死者が訪れる合図である。それは悲哀の経験だが、私たちに寄り添う死者の実在を知る、慰めの経験でもある。」
「悲しいと感じるそのとき、君は近くに、亡き愛する人を感じたことはないだろうか。ぼくらが悲しいのは、その人がいなくなったことよりも、むしろ、近くにいるからだ、そう思ったことはないだろうか。
もちろん、姿は見えず、声は聞こえない。手を伸ばしても触れることはできない。(中略)でも、ぼくらは、ただ悲しいだけじゃないことも知っている。心の内に言葉が湧きあがり、知らず知らず、声にならない会話を交わし、その人を、触れられるほど、すぐそこに感じたことはないだろうか。ぼくは、ある。」(『魂にふれる』 p7〜 p11)
いとうせいこう氏は、こう続ける。「つまり生者と死者は持ちつ持たれつなんだよ。決して一方的な関係じゃない。どちらかだけがあるんじゃなくて、ふたでひとつなんだ」(『想像ラジオ』p138)
DJアークは、この世でもあの世でもない「中有」にいるらしい。
「今まで僕が想像力こそが電波と言ってきたのは不正確で、本当は悲しみが電波なのかもしれないし、悲しみがマイクであり、スタジオであり、今みんなに聴こえている僕の声そのものかもしれない」彼はそう呟く。すると、ツイッターのような同時多元放送を通じて、沢山のリスナーがポリフォニックに次々と声かけをし、DJアークを励ます。「想像せよ」「想像するんだ」と。こうして悲しみ愛する「悲愛」というチャンネルを通じて死者と生者が手を取り合うラストは本当に感動的であった。
その余韻の中で、番組を終えるDJアークが最後にかけた曲は、「私」がリクエストした、ボブ・マーリーの『リデンプション・ソング』だ。
原子力など恐れるな
奴らに時まで止めることはできやしない
あまりにも長いこと 奴らは
俺たちの予言者を殺しつづけてきた
俺たちは、傍観していただけだった
ある者は それは聖書に書かれているという
そして 俺たちは
予言の書を完成せねばならない
この自由の歌を 一緒に歌ってくれないか
なぜなら、俺が今まで歌ってきたのは
すべて救いの歌だけだ
そう 俺の歌ってきた歌は
すべて救いの歌なんだ
宮沢章夫、シティボーイズと共に芝居を続ける現役の役者であり、ヒップホップの草分けとして反原発デモではラップを披露し、三社祭では御輿を担ぐ。いとうせいこう氏はとことん格好いい。
作家としては、この『想像ラジオ』を16年の沈黙を破って書き上げた。いとう氏の奢らない真摯な思いが、読者の心に確かなメッセージとして真っ直ぐに突き刺さる傑作である。

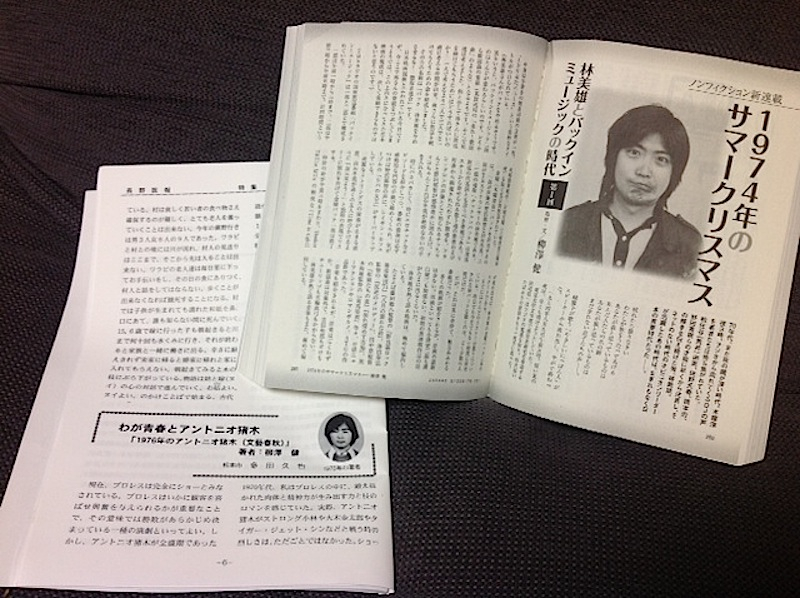




最近のコメント