■毎週水曜日の午後は休診にさせていただいている。
週の真ん中に、個人的に自由に出来る時間があると何かと便利なのだ。例えば、歯医者さんへの通院。実際いま、伊那市駅前の「中村歯科医院」へ水曜日の午後通っている。
ただ、この8月末から10月末までの2ヵ月間は、毎年「上伊那医師会付属准看護学院」での小児看護の講義が水曜日の午後3時半から5時まで計8回あって、講義の予習準備とか試験問題を作ったりとか、けっこう大変だったのだ。まる10年間お務めしたのでそろそろ引退したいと思い、伊那中央病院小児科の木下先生に講師を代わってもらえないか打診したら、思いがけず快く引き受けてくれたのだ。木下先生、ほんと有難うございました。
■という訳で、今年は准看護学院の講義が9月10月の水曜日の午後は入っていない。ありがたいなぁ、ほんと。
で、かねてから映画館で是非見たいと思っていた、原田芳雄さんの遺作『大鹿村騒動記』が伊那旭座にかかっていたので、早速今週の水曜日の午後に伊那旭座へ行って見てきました。東映配給だったんだね、知らなかった。しかも! 前売り券なしで入場料が1000円均一。これって、けっこう英断だよなぁ。映画を見る前からすっごく得した気分だ。
映画館に入ると、思いのほか入場者が多い。と言っても、ぼくより年配の方々が10数人、既に着席していた。伊那旭座にしては「大入り」のほうなんじゃないか?
■場内が暗転し、スクリーンに光が照射される。最初はお決まりの「不法録画防止啓発ビデオ」だ。その次は、次回上映の映画の予告編かと思ったら、いきなし本篇が始まった。
美しい大鹿村の遠景をバックに白字で『大鹿村騒動記』のタイトルが縦書きで現れる。けっこう癖のある字だが下手ではない。味がある字だ。これはエンドロールで明かされることなのだが、主演の原田芳雄さんが書いた字なのだそうだ。
映画『大鹿村騒動記』は、伊那市長谷市ノ瀬から南へ「ゼロ磁場」で有名な分杭峠を超えれば、下伊那郡大鹿村となるのだが、その長野県に実在する「大鹿村」でオールロケされた映画なのだった。変に気負いがなくて、フットワークも軽く何気なくさらっと撮影された映画なのだが、往年の名優そろいぶみの贅沢なキャスティングで、主演の原田芳雄をもり立てているのだ。
ああ、いいなあ。ほんといい映画だった。満足しました。評点は、ちょっとオマケして星4っつ半! ★★★★☆
■やはり、映画の基本は「男2人女1人」の三角関係だ。古くは『冒険者たち』って、同じ話を「佐藤泰志」の小説『君の鳥はうたえる』『そこのみにて光輝く』の感想文で書いたばかりだな。
で、「この映画」もちゃんと「それ」を踏襲しているのだ。
ただ、圧倒的に違うことは、主人公を含む3人組(原田芳雄、岸部一徳、大楠道代)が、青春真っ直中にあるのではなくて、団塊世代の既に60歳を超えた「年寄り」であることだ。
■じつは「大鹿歌舞伎」を題材にしたドラマと映画が以前にもあった。NHK長野局が制作した単発ドラマ『おシャシャのシャン!』(2008年1月放送)と、後藤俊夫監督の映画『Beautyうつくしいもの』だ。
この『おシャシャのシャン!』には、原田芳雄さんも重要な役どころ(ヒロインの父親で大鹿歌舞伎では主役を演じる)で出演していて、この撮影で原田さんは実際に大鹿村を訪れ「大鹿歌舞伎」を知ったのだった。
このドラマもなかなかよくできた脚本で面白かったのだが、舞台で演じられる歌舞伎の演目の内容と実際のストーリーが絶妙にリンクしてラスト盛り上がる『大鹿村騒動記』の方に軍配は上がるな。ほんと、荒井晴彦と阪本順治の脚本はよく書けている。
■映画の中で演じられる大鹿歌舞伎は「『六千両後日文章』 重忠館の段」で、原田芳雄さんが主役を務めるのが「平景清」。おお! 知ってるぞ「景清」。落語の演目にある、あの「景清」ではないか! 桂米朝と桂文楽のCDで持っているし、新宿末廣亭で四代目三遊亭金馬が演じたのを生で聴いた。それに、何よりもあのNHK朝の連続テレビ小説『ちりとてちん』で、徒然亭草々が一生懸命稽古していた「ネタ」じゃないか。
落語では、腕のいい木工職人だった定次郎が失明してしまい、再び目が見えるようになりますようにと、清水の観音さんに願掛けで1000日通う。この観音さんは、むかし平家の落人の景清が「源氏の世は見たくない」と自分で両眼をくり抜いて納めたという所。その満願成就の日、結局定次郎の眼は見えるようにはならなかった。ところがその帰り道、空がにわかにかき曇り暗雲垂れ込め車軸の雨。ガラガラ、どしーん!と定次郎に雷が落ちた。さて、それから……
■映画に出ている役者がみな、一癖もふた癖もある渋い役者さんばかり。おけつ丸出しで温泉にダイブする岸部一徳、その鹿塩館の主人に小野武彦(「踊る大捜査線」スリーアミーゴスの人ですね)。そして、リニア新幹線誘致で対立する土建屋社長役の石橋蓮司と、中国の勤労研修生にバカにされている白菜農家の小倉一郎。久しぶりだなぁ、小倉一郎。『俺たちの朝』以来か。
あと、貫禄の三国連太郎。あのお歳で大鹿村のロケに参加されたのだなぁ。晩秋の大鹿村と青い空をバックに、三国連太郎が遠くシベリアの地で死に果てた友の墓に木彫りの仏を供えるシーンが重く美しい。
それから、何と言っても大楠道代がいい。原田さんと共演した鈴木清順『ツィゴイネルワイゼン』の時とぜんぜん変わらない色っぽさじゃないか。イカの塩辛の瓶詰め。いいなぁ。
若いところでは、松たか子もよかったが、『ちりとてちん』で徒然亭四草を演じて、一躍注目を集めた加藤虎之助がちゃっかり出ている。みなが一丸となって、主役の原田芳雄さんを盛り立てている。その雰囲気がスクリーンに溢れているのだ。
とにかく、スクリーンの原田芳雄さんがカッコイイ。
テンガロンハットにサングラス。それに黄色いゴム長靴。似合っているのだ。これ以外ないって感じでね。
彼は『ディア・イーター』という名前の鹿肉食堂をやっている。あはは! ディア・ハンターじゃなくってね。あと、原田さんが松たか子に「木綿のハンカチーフ」を歌って聴かせるシーンがあるのだが、何故か下手。あんなに歌が上手い人なのにね。可笑しかったな。
映画では案外、原田芳雄さんのアップシーンが少ない。わりと離れて画面の片隅に原田さんを配置している。アップは一番重要なシーンで使われるからだ。
もう一回、見にいってもいいかな。この映画。
【追伸】映画『大鹿村騒動記』の監督と脚本家「阪本順治 × 荒井晴彦 対談(前編)」 「阪本順治 × 荒井晴彦 対談(後編)」が、たいへん興味深かったです。






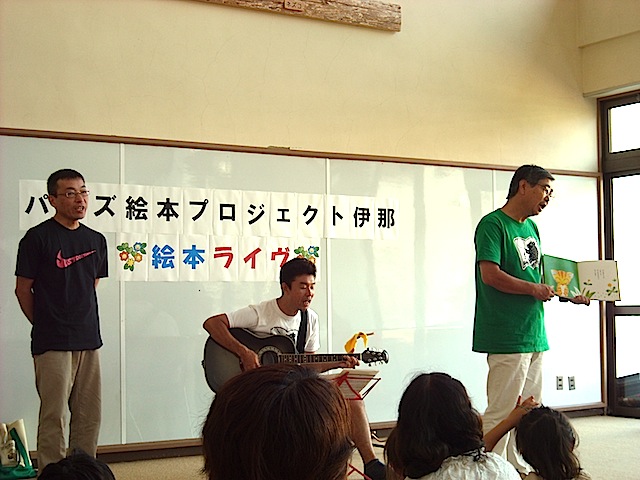



最近のコメント