エリック・ドルフィーを聴いている
■ときどき、無性に「ドルフィー」が聴きたくなるのだ。
エリック・ドルフィー『ベルリン・コンサート』より1曲目「Hot House」を聴いている。やっぱり、ドルフィーはチャーリー・パーカーが大好きなんだろうなあ。だからこそ彼は、パーカーのソロと同じフレーズを絶対になぞらないように、周到に注意深く演奏している。まるでデレク・ベイリーみたいじゃないか!(2014/02/19)
このところずっと、エリック・ドルフィーについて考えているのだけれど、きっと彼の脳味噌はブラック・ボックスだったんだろうな。インプットとアウトプットの差が尋常でなくかけ離れている。彼の脳の高性能なアンプリファイアーの不思議を思う。(2014/02/19)
それにしても、あの有名な「おでこのコブ」をドルフィーはずっと気にしていて、手術で切除してしまっていたとは、ぜんぜん知らなかったぞ。
・『エリック・ドルフィーの瘤』(菊地成孔「粋な夜電波」第55回より)
・『続・ドルフィーの瘤』(菊地成孔「粋な夜電波」第59回より)
『JAZZ 100の扉』村井康司(アステルパブリッシング)を買って読んでいるのだが、エリック・ドルフィー『アウト・トゥ・ランチ』の解説(79ページ)にこんなことが書いてあった。
「そして何より恐ろしいのは、彼の演奏が『何を言っているかはわからないが、そこには確固としたセオリーが確実に存在していて、音楽総体が発する意味は確実にこちらに伝わってくる』ということにあるのだ」(中略)
「しかしそこにドルフィーのアルトやバス・クラリネットのよじれたフレーズが乗ると、世界は『正確無比に狂った時計』のような様相を示し始めるのだ。」 なんてスルドイ分析なのだろう。
YouTube: Charles Mingus Sextet in Europe, 1964
ただ、ドルフィーに関する考察で、「あっ!」と思ったのは、何と言ってもSF作家・田中啓文氏の文章。
・「エリック・ドルフィー(1)」(田中啓文 ビッグバンド漫談より)
・「エリック・ドルフィー(2)」(田中啓文 ビッグバンド漫談より)
・「エリック・ドルフィー(3)」(田中啓文 ビッグバンド漫談より)
■それから、バリトン・サックス奏者で、フリージャズ関係に詳しい、吉田隆一氏の分析が、もっともっと聴きたいと思うのは、僕だけではあるまい。





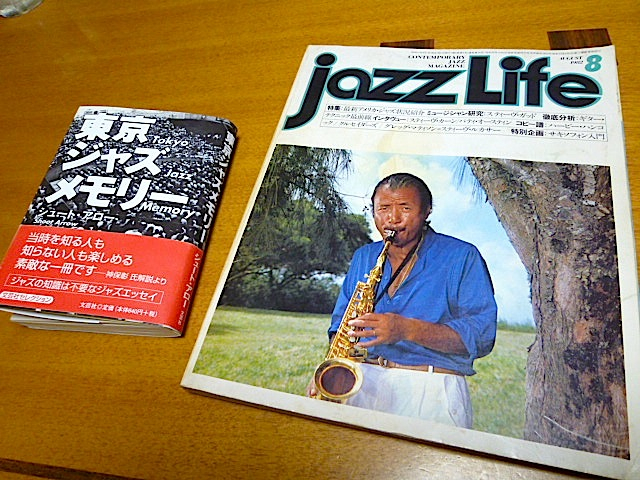










最近のコメント