■昨日の日曜日は、はっぴいえんどの名曲『12月の雨の日』を思わせる前日の土曜日とは打って変わって、雲ひとつない快晴。しかも、季節はずれの暖かさだ。
午前9時半から2時間、高遠福祉センターでアンドレア先生から「入試英語特講」を受ける長男を車で送って、向かいの「ポエム」でコーヒーでも飲もうかとも思ったのだが、暖かだったからエンジンを切った車の中で読書。島村利正『繪島流罪考』を読む。この短篇が載っている『島村利正全集・第二巻』は借りてもう随分と延滞していて、今日こそは高遠町図書館に返却しなければならなかったからだ。
江島は結局、月光院といい仲になった御用人、間部詮房が「大奥」の全権力を握っていることを嫌う反対勢力によって、クーデターの餌食にされたのだな。それなのに、一番の問題人物たる間部詮房は、一切のお咎めも流罪もなく、単に越後へ左遷されただけで歴史上から静かに消え去った。ずるいじゃないか、ほんと。許せないぞ。
■午前十時を過ぎたので、高遠町図書館へ行って本を返却。もし、図書館長さんがいたら、先日、ワサブローさんが高遠を訪れて島村利正生家の菩提寺で墓参りしたことを話し、さらには、来年が「島村利正生誕100周年」に当たるので、ぜひ記念イベントをしましょう! と提案するつもりだったのだが、あいにく図書館長さんは非番でいなかった。残念無念。
いったん伊那へ帰って、わが家では日曜日の昼飯は「蕎麦」という決まりがあったから、高遠なら「ますや」だな、と妻・次男を車に乗せ再び高遠へ。午前11時半過ぎに講義が終わった長男をピックアップして、高遠バイパスを北に少し行って「ますや」へ。
12時前だから楽勝だろうと思ったら大間違い。すでに店は満席じゃぁないか。駐車場も、県外ナンバーの車でいっぱいだ。仕方なく、上の段の店舗用車庫の前に駐車する。そうは言っても、この日はまだ店の外にまでは行列はできていなかった。ラッキーだ。入店後10分足らずでテーブルに着く。店主と女将さんの二人だけで店を切り盛りしていて大忙しだ。
ひと通りの注文がで終わるのを待って、ぼくらの番になった。次男は「高遠そば」。妻は「おろし高遠そば」で、長男は「鴨ざる」を注文。ぼくは最後まで迷って、結局「玄そば」+追加(合計3枚)にした。
注文後は案外はやく蕎麦が出た。実にきれいな蕎麦だ。つやつやと透き通って輝いている。洗練されていて喉ごしも申し分ない。なるほど、これなら都会の蕎麦通がはるばる遠く高遠まで何度も通ってくるワケだ。蕎麦の見た目と喉ごしは、むかし松本の女鳥羽川沿いにあった蕎麦屋「もとき」で食った蕎麦に近い印象。
もちろん、「ますや」へは以前から何回も食いに来ているのだが、来るたびに「蕎麦が美味くなっている」のだよ。そこが凄い。常に地道な努力と、たゆまぬ前進を続ける店主の心意気のたまものだな。いや、ほんと旨かったデス。でも、俺以上に美味そうに食っていた、長男の「鴨ざる」を次回は注文しようかなぁ。あの、網で炙った太いネギと鴨肉を「この世の極楽」といった風情で食っていた長男に、ちょっとだけ嫉妬したのだった。
■高遠から伊那へ帰り、妻子を自宅で降ろし一人また車上の人となる。坂本さんの「やまめ堂」へ行って、児童文学の季刊誌『飛ぶ教室』最新号を購入しなければならなかったからだ。中央橋を渡って左折し、幸福の科学の建物の手前を右折し、小松眼科の横を左折。仁愛病院を通り過ぎれば、目指す「やまめ堂」だ。だがしかし、「お休み」のふだが冷たく店舗ドアにかかっている。あちゃ。
仕方なく、再びバイパスに出て左折し「伊那市図書館」へ。もしかしたら伊那図書館館長の、平賀研也氏に会えるかもしれない、そう思ったからだ。
■さて、ぼくの感は正しかった。平賀館長さんは確かに伊那図書館にいたのだ。やった! アポなし急遽面会ごめんなさい。
で、ワサブローさんが高遠を訪れた経緯と、来年の6月23日(土)の夕方、信州高遠美術館ロビーで「ワサブロー・シャンソン・コンサート」開催が決定したことを話した。ついでに、来年が「島村利正生誕100周年」であるから、ぜひ記念イベントを企画して下さいと懇願する。
さらに、島村利正の高遠を舞台とした著作『庭の千草』や『仙醉島』『城趾のある町』に記された地籍から、『高遠文学マップ・島村利正編』を「iPad」上で構築できますよ! と僕は話した。
でも、どの程度平賀図書館長さんが興味を持たれたか、まったくわからない。少しでも記憶の片隅に残ってくださればうれしいな。
このブログは、平賀館長さんはたぶん読んでいないだろうから、過去にぼくが島村利正氏に言及したページにリンクを張っておきますね。
・「島村利正」がなぜかマイブーム
・島村利正の小説に登場する、古きよき高遠の人と街並み
・『妙高の秋』島村利正を読む
・今月のこの1曲「わたしが一番きれいだったとき」ワサブロー
・不思議なご縁の男性シャンソン歌手ワサブローさん。
■伊那図書館から自宅へ戻ると、午後2時半過ぎだった。
いやぁ、ごめんごめん。この日は伊那東部中1年生で、陸上部・長距離班に所属する次男に頼まれて、鳩吹公園近くに設置された「クロスカントリー・コース」をいっしょに走る約束だったのだ。
で、鳩吹公園に着いたのが午後3時過ぎ。もうじき日が暮れる。
ところで、その「クロスカントリー・コース」は何処にあるのだ?
風車がある駐車場に車を停めて、左側から西へ50mほど昇ると看板があり、そこから左へ下って行くと確かに「クロスカントリー・コース」があった。
今年の春に整備されたコースなのだが、この晩秋にでもなると、落葉が全面を覆い、春に散布した「ウッド・チップ」もすっかり蹴飛ばされていて、結局どこが整備されたジョギング・コースなのかぜんぜん判らない状態になっていた。
とはいえ、最近でもこのコースを訪れる人がいるとみえ、落葉に足跡が残ってコースは維持されていたのだった。
全長1km強のコースで、8の字で回れば 1.2km くらいはあったな。三峰川のサイクリング・ロードは吹きっさらしで、冬場は冷たい強風に難儀するのだが、ここの林間コースは不思議とほとんど風がなくてありがたい。
しかし、とにかく「アップ・ダウン」がきつい。最初の1周で、ぼくはバテバテになった。
でも、息子とは「30分は走り続ける」と約束したから、仕方なく走り続けた。4周した。ただ後の2周は、8の字コースではなく、0の字にして、本来は長いキツイ登りになるコースを易々と下って済ませたのだった。ごめんな、ズルして。息子よ。
■そんなワケで、この日は疲れた。
白菜と豚肉を「S&Bおでんの素」で茹で、柚胡椒で溶いていただく鍋を夕食に食べ終わり、アルプスワイン旬醸「コンコード赤」を3杯ほど飲んだので、午後8時すぎにはすっかり酔っぱらって寝てしまい、休み無しの寝不足状態が続いていたこともあって、結局この日は翌朝の午前7時半まで延々と寝続けた。
計算すると、11時間も寝ていたことになる。ほほ2日分だ。
あいや、たまげたぜ。

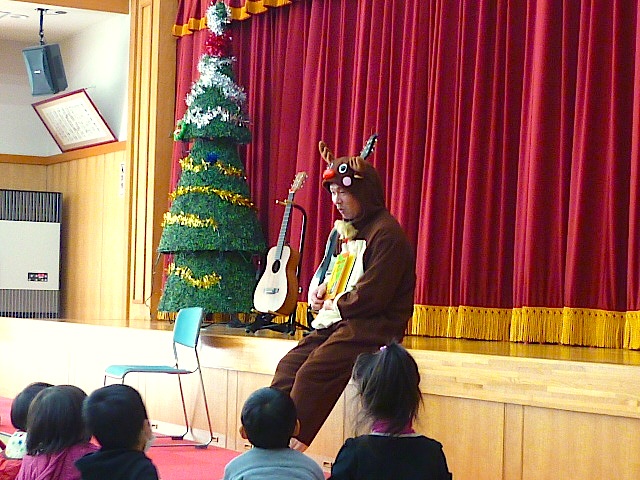







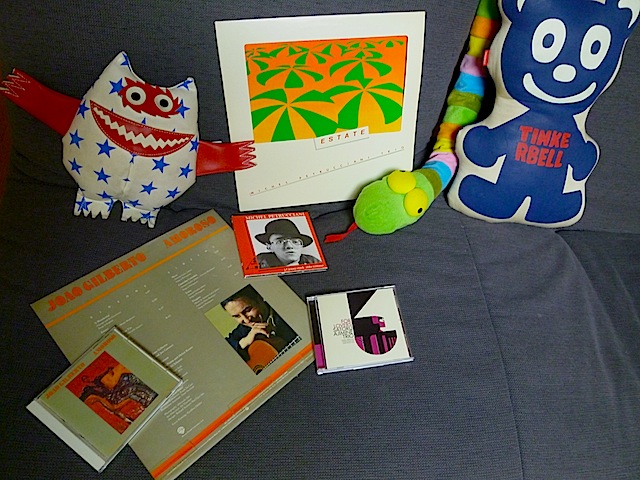



最近のコメント