カマシ・ワシントン(さらに続き:マルサリス兄弟のこと)
■前掲の「日本人にジャズは理解できているんだろうか」という村上春樹氏の論考の一番のポイントは、ブランフォード・マルサリスの発言が発端となっていることだ。
村上春樹のエッセイ集『やがて哀しき外国語』(講談社文庫)に収録された「誰がジャズを殺したか」の中で、村上氏はその張本人として「マルサリス兄弟」の名前をあげているし、『意味がなければスイングはない』村上春樹(文藝春秋)では、161ページから「ウィントン・マルサリスの音楽は なぜ(どのように)退屈なのか?」という章がわざわざ設けられている。
つまり、村上氏は「マルサリス兄弟」のことがあまり好きではないみたいなんだな。本文ではあくまでも紳士的に「マルサリスさんが仰ることは、よーくわかりますとも」と書きつつ、その行間では、「それを、よりによって『あんた』には言われたくなかったな」って、村上氏はたぶん言っている訳ですよ。
・
結局のところ、残念ながらジャズというのはだんだん、今という時代を生きるコンテンポラリーな音楽ではなくなってきたのだろうと思う。冷たい言い方かもしれないけれど、 僕はそう感じるし、思う。
もし僕が1952年にアメリカにいたら 、何があったってNYに行ってクリフォード ブラウンの ライブをきいていただろう。1960年にアメリカにいたら、やはり同じ様にジョン・コルトレーンと キャノンボールとビル・エバンスの加わったマイルス・デイヴィス・セクステットを必死に聴いていただろう。
何も新しいジャズが嫌いだというのではない。新しいジャズだって聴けば楽しいし、やっぱりジャズっていいなあと思うことだって多いのだ。でもそこには心を深く揺り動かす物がない。いまここで何かが生まれつつあるのだという興奮が無い。僕としてはそういうものに、かつての熱気の記憶で成立しているようなものに、余り興味が持てないというだけの事なのだ。(中略)
・
でもこの演奏を聴いていて思ったのは、「結局のところ、マルサリスたちの世代にとっては、ジャズという音楽は一種の伝統芸能に近い物になっているんだろうな」という事だった。
ウイントン・マルサリスは素晴らしい才能を持った若者である。そして実に深く、真面目にジャズを研究している。ルイ・アームストロングから、キャット・アンダーソン、クリフォード・ブラウン、マイルス・デイヴィス、にいたるまでみんなが彼にとっての偉大な英雄なのだ。そしてウイントンは彼らの響きを見事に現代に再現することが出来る。その音色は惚れ惚れする位美しいし、テクニックは小憎らしいくらい完璧である。
でもそれだけではない。彼の演奏には愛情が、慈しみのようなものが溢れているのである。 それはおそらく過ぎ去ってしまったものへの、今消え行こうとしているものへの慈しみである。
僕は個人的には、ウイントン・マルサリスの演奏がとくに好きというわけではない。ウイントン・マルサリスの演奏にはまだ「ウイントン・マルサリスの演奏でなければ」というだけの本物の熱気がない。ここで今、この目の前で何かが生まれていると聴衆に感じさせる要素が希薄である。でもそれはそれとして、彼の演奏には人を強くひきつける何かがあることも又確かである。
・
しかし世間には「マルサリス一派叩き」の動きもある。ウイントンは若い世代のジャズ・ファンの間にカリスマ的な人気を持っているし、ブランフオード・マルサリスはテレビの人気番組「トウナイト・ショウ」の音楽監督兼レギュラー・バンド・リーダーになった。彼らは今日のジャズ界において、60年代のケネデイ兄弟みたいな影響力を持った存在になりつつあるように見える。そういうことに対して不快に感じている人々が多くいたとしても決して不思議はない。
先日「NYタイムズ」の日曜版にピアニストのキース・ジャレットが寄稿して、マルサリス一派(具体的な名前こそ出さなかったけれど、ちょっと読めば彼がマルサリス兄弟を念頭において書いているのは一目瞭然である。)を批判していた。
「最近の若手の黒人ミュージシャンたちは実にうまくジャズを演奏する。でも彼らの創造性というのは一体どこにあるのだ。」というのがその文章の骨子だった。でも僕は思うのだけれど、たぶんマルサリスたちの考える創造性というのは、名前こそ同じだけれど、実は全然違った場所で違った空気を吸って生きている同名異人のようなものではないのだろうか。
キース・ジャレットたち60年代の世代にとっては、音楽というのは戦い取るものだった。 彼らにとっての創造行為とは、多くの場合において先輩のコンサーヴァテイブな演奏家達との絶え間の無い戦いだった。負けるか勝つか、否定するか否定されるかかという熾烈な戦いだった。そこに彼の言う「創造性」が生まれた。
僕は正直言って、キース・ジャレットという演奏家の「創造性」を余り高くは評価しない人間だけれど、それでもそこに「創造性」への希求があったことを認めるのにやぶさかではない。
でもマルサリスたちの世代にとっては、ジャズという音楽はもはや反抗すべき物ではなく、それに感動し、そこから学び取っていくべき音楽なのだ。彼らにとっては、それはある意味では既に一度閉じてしまった環である。彼らにとっては、それは古くて素晴らしい物が詰まった宝箱の箱のような物である。彼らはそのような発見に大きな喜びを感じ、スリルを感じるわけだ。
それはある意味では「若手の黒人ミュージシャン」にとってのルーツ探しであり、それなりにヒップな行為なのだ。そういう彼らのジャズという音楽に対する観念・発想そのものが、キース・ジャレットの世代のそれとは全然異なった物なのだ。その根本的な相違をキース・ジャレットはやはり認識しなくてはならないと思う。
「反抗しろ、戦い取れ」と言われても、マルサリスたちにすれば「そんなこと言ったって、いったい何に反抗すればいいんだよ」とただ肩をすくめるしかないのではないか。逆にいえば、マルサリスたちは、「彼らに反抗しなくてはならない」と思うほどには、キースたちの世代の音楽を評価していないと言う事になるのではないか。そしてそういうところにもまた、キースの深い苛立ちがあるのだろう。
(『やがて哀しき外国語』村上春樹:講談社文庫「誰がジャズを殺したか」より抜粋)
・
■これを読んで笑ってしまうのは、村上さんの「キース・ジャレット嫌い」は有名な話だから、さらに混乱してしまうんだな。『意味がなければスイングはない』(文藝春秋)の169ページには、こんなことが書いてある。
・
正直に言わせていただけるなら、僕はキース・ジャレットの音楽の胡散臭さよりは、ウィントン・マルサリスの音楽の退屈さの方を、ずっと好ましく思っている。そして同じ退屈さでも、チック・コリアの音楽の退屈さよりは、こちらの方がよほど筋がいいと感じている。(『意味がなければスイングはない』p169)






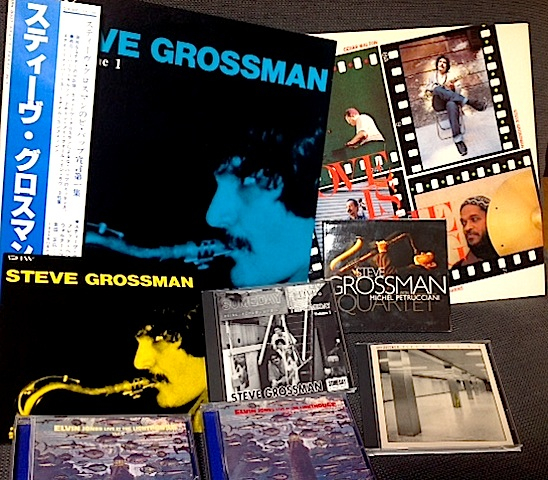

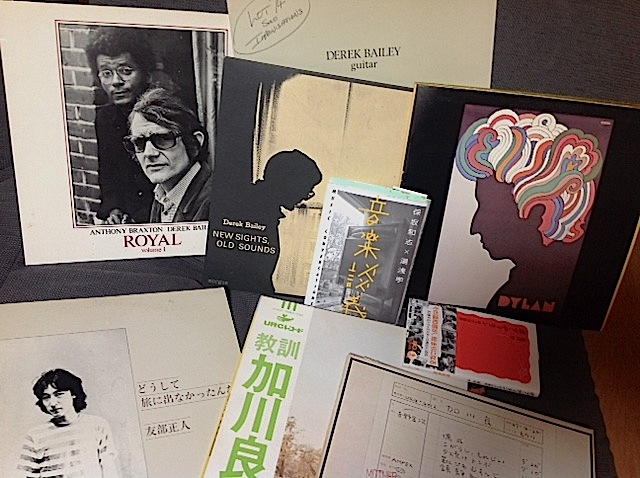




最近のコメント