■もうずいいぶんと前に読了した本なのだが、なかなか感想が書けないでいる。
で、無理に感想を書くのをやめて、印象に残ったフレーズを抜粋することだけにしよう。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■その前についでに言うと、この本を読んだ後に『小田嶋隆のコラム道』(ミシマ社)を読んだのだが、これはつまらなかった。本の帯には「なんだかわからないけど めちゃめちゃおもしろい」と、文教堂書店浜松町店の大波由華子さんは書いているが、ほんとうにそう思ったのか? そうか。人はいろいろだからなあ。
ぼくが「この本」で一番面白いと思ったパートは、第13回「裏を見る眼」に書かれた塩谷瞬「二股愛」報道に関する考察。でも、それってこの本に期待した内容ではない。小田嶋氏のいつものコラムだ。
たぶん、本の企画段階では「これはいける!」と、編集者ともの凄く盛り上がったに違いない。ところが、実際に連載が始まってみて「この企画は失敗だった」と、小田嶋氏は気づいてしまったのではないか。だから筆が進まず5年以上もの歳月が過ぎ去ったのだろう。
もともと「コラム道」と『道』って書かれているからね。いわゆる文章読本ではないことは読む前から判っていたし、そういった「小手先のテクニックを伝授」みたいな記載は期待していなかった。
でも、「あとはたくさん読んでたくさん書けば、いやでも文章は練れてくる。」(p188) って、それが結論じゃぁ、あまりに淋しいのではないか。
なるほどなあと感心した部分もあった。
第4回「会話はコラムの逃げ道か」の後半部分。
かと思うと、会話の上では、才気煥発に見える人が、文章を書かせると、どうにも散漫で支離滅裂である例も珍しくない。というよりも、もしかして、打てば響くタイプの人間の多くは、文章が苦手であるのかもしれない。
なぜだろう。
どうして、アタマの良い人が、良い文章を書けないというようなことが起こりうるのだろうか。
おそらく、このことは、魅力的な会話を成立させる能力と、マトモな文章を書くための能力が、まったくかけはなれているということに由来している。(中略)
彼らはテニスプレーヤーに似ている。
速いサーブに対応する反射神経と、意想外のドロップショットに追いつくスピードを持った彼らは、会話という限られたコートの中では、どんなタマでも打ち返すことができる。(p53〜p55)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
■閑話休題■
■『苦界浄土』石牟礼道子は、たしか大学生のころ講談社文庫版で買って読んだ記憶がある。いやまてよ。買っただけで、最後までちゃんと読み通さなかったかもしれない。つまり、「水俣病」がリアルタイムだった僕でさえ、その程度なのだ。
ちなみに、世界的に有名な小児科の教科書である「ネルソンの小児科学」の載っている「水俣病」の項目は、前々の信州大学小児科学教室教授であった、故・赤羽太郎先生が執筆している。(ぼくが持っている「ネルソン小児科学」はそうなのだが、現在出回っている版がどうかは知らない。)
「水俣病」なんて、数十年も前に終結した公害病っていう認識しかなかったぼくは、「この本」を読んで恥ずかしく思ったのだった。過去完了形なんてもってのほかで、2世3世4世と引き継がれて、現在進行形で今でも20代の若い人たちに「水俣病」が発症しているということを、この本を読んで初めて知った。ごめんなさい。
■それから、写真家・藤原新也氏といえば、『メメント・モリ』に載ったあの有名な写真。そう、「人間は犬に食われるほど自由だ」とキャプションが付けられ「黄昏のガンジス河畔に流れ着いた水葬死体に野犬ががつがつ食らい付いている」あの写真がまずは目に浮かぶ。
でも、「ここ」を読むと、あの写真以外には死体をカメラに撮したことはないのだそうだ。そうだったのか。
藤原:水銀というのはつまり味も臭いもないということですね。まるで放射能そっくりだ。感じられないものほど怖いものはない。
石牟礼:いまも若い人たちに発症例が見受けられるんです。
藤原:えっ、いまもですか?
石牟礼:はい、二十代の終わりぐらいの人たちが発症しているそうですけれども、国が特別措置法というものをつくって、裁判をしないこと(後略)
藤原:それで水俣の、たとえば猫が狂いはじめたというのがいつごろですか。
石牟礼:それは昭和三十年前後ですね。(『なみだふるはな』石牟礼道子・藤原新也・河出書房新社 p53~54)
-----------------------------------------------------------------------------------------
石牟礼:鹿児島と宮崎と熊本の三県の境くらいに曽木の滝というのがあるんですけれども、チッソはそこに電力会社をつくって、まず電気を引いたんですね、水俣へ。(中略)
それを聞いた人たちが、「そんなのが来るなら、うちの山にも電信柱を通してほしい」「うちの田んぼにも通してください」と。「そっちのほうには行かれん」と会社の人たちがいうでしょう、「それなら電信柱の影なりと、うちの畑にも映るごつしてくだはりまっせ」と(笑)。なんていうか、いじらしいんですよ。(中略)そうやって電気を引いてきて、その電球が灯った晩のことは私もはっきり憶えています。(中略)
藤原:やっぱり電気ですか、はじまりは。電気にはじまり電気に終わる。(中略)
石牟礼:水俣にとっては会社は恩人と思っていたのです。それはいまでも根強いですよ。
(『なみだふるはな』「光」 p83~86)
------------------------------------------------------------------------------------------
藤原:憎しみとか憎悪というのは人間が他者に持つネガティブな感情の中では最も重篤なものだと思うのです。その「憎い」という言葉を聞いて僕の頭に思い浮かんだのは旅したアラブやイスラム世界でした。パレスティナがいい例ですが、あの世界ではいたるところで憎しみの連鎖がいつまでもつづき、いまに至っている。
その憎しみの根源には何があるかというと、土地の略奪と喪失なんです。イスラム世界というのは、たとえばイランは住める土地が少ない。だから人間の住める沃土はすごく貴重です。
僕が今回の強制避難区域で聞いた「憎い」という言葉の根源には、そのイスラムの憎悪の根源にある、自分が住んでいる「土地を失う」に似た意味があると思うんですね。つまりある日、代々伝わり子どものころから住み慣れた土地や家を強制的に略奪されたわけです。この悲しみや怒りは、放射能を浴びるよりずっと大きい。(中略)
だけど、原発の強制避難区域というのは事実上帰れない。庭先の除染は可能ですが、広大な野山までの除染は不可能です。そういう仕打ちを自然がやったとするならあきらめもつくだろうが、人がやったんですね。
日本というのは確かに異民族も同居はしていますが、世界の国に比べると圧倒的に一国家一民族的色合いが濃い。そういうものの中で、和の精神とか空気を読んで他人に合わせるという曖昧な他者との処方が機能してきたわけですが、思うにこのイスラム世界のように、同民族を同民族が憎悪するという心の版図は日本にはなかったように思うのです。そういう意味では神代の昔以来初めてここで小さな民族分裂が起こっていると、現場を踏んでそのように感じるんです。(中略)
石牟礼:(前略)世間の人たちもわかってくれなかった。なんでこう苦しまなければならないんだと考えて、「あんたたちは誰も病まんけん、代わって俺たちが病んでいるんだ」という気持ちになられるのです。(中略)
それで、「知らんということは罪ばい。この世に罪というのがあるのなら、知らんということがいちばんの罪。それで、知らん人たちのためにも、自分のためにも祈ります」と。(中略)
「あんたたちのおかげでこういうふうになった」とはおっしゃらない。代わって病むとおっしゃる。これは現代の聖書ですよね。だけど、聖者といったって、その人たちの苦しみを和らげることはできないんですね。近代というのは罪に満ちていると思います。
「道子さん。私は全部許すことにしました、チッソも許す。私たちを散々卑しめた人たちも許す。恨んでばっかりおれば苦しゅうしてならん。毎日うなじのあたりにキリで差し込むような痛みのたっとばい。痙攣も来るとばい。毎日そういう体で人を恨んでばかりおれば、苦しさは募るばっかり。親からも、人を恨むなといわれて、全部許すことにした親子代々この病ばわずろうて、助かる道はなかごたるばってん、許すことで心が軽うなった。
病まん人の分まで、わたし共が、うち背負うてゆく。全部背負うてゆく。」
(『なみだふるはな』「憎しみと許し」 p129~135)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
石牟礼:(前略)不知火海百年を語ってください、という会をしたんですよ。怪我をするまで、わが家でしてました。限られた漁師さんに来てもらって。ともかく海のことをお聞きしたいと思って来てもらっておりましたけれども、いろいろ教えてくださって。ほんとうかお話かは知りませんが、
「あんな、道子さん、知らんと? タチウオは頭が三角になっとるでしょうが」
「はい」
「あの三角頭が縦になって立ち泳ぎすっとばい。そしてお日さまが出なはるころになると、さーっとお日さまが山の端から出なさると、いっせいに三角の頭を波の上に出してな、合掌しよっとばい。知らんじゃったろ?」
(『なみだふるはな』「光明」 p152)
■チッソが来る前の水俣も、原発が来る前の福島も、それはそれは風光明媚で、「自然」とその土地に暮らす「人間」とがお互いに畏怖・尊敬しながら生きていた場所だ。それが、水俣では60年経っても未だに新たな患者さんが発症していて、福島第一原発はたぶん100年経っても収束しないのではないか。
怖ろしいことだ。悲しいことだ。





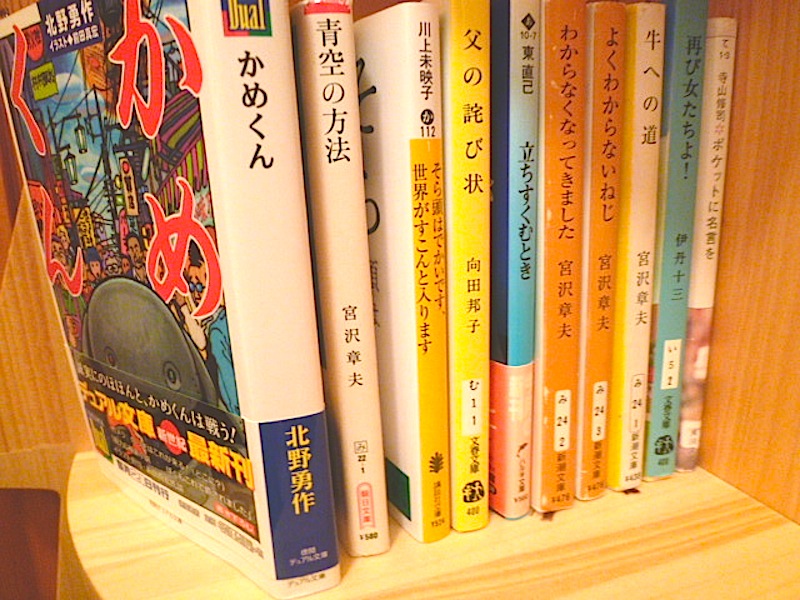


最近のコメント