■隣の席の人に少しだけ遠慮しながら、役者さんのちょっと変なセリフに思わず笑って観ていたら、ふと足下をすくわれたようになって、何とも居心地が悪くなり訳が判らなくなってしまった芝居『ヒネミの商人』。
以下、感想ツイートを少し改変してまとめました。
■夜中に連続ツイートしたので、ちょっとアレなんですが、失礼ごめんなさい。
------------------------------------------------------------------------
■先達ての日曜日(3月23日)日帰りで東京に行って来た。天気予報では暖かい春の日和だって言うから、ジャケットにワイシャツだけで特急あずさに乗ったのだが、新宿に着いたら皆冬の格好で焦った。確かに寒いぞ。最初に行ったのは「ビックロ」。朝から人でいっぱいだ。
「ビックロ」へ行ったのは、息子へのお土産に「SHURE」のイヤホンを買うためだ。でも売り場へ行ってみたら、DENON のワイヤレス・イヤホンが安くなってたので、結局こっちにした。DENON インナーイヤーヘッドホン AH-W150
■その後は、ディスクユニオン「新宿ジャズ館」へ行き、欲しかったCDの中古盤をゲット。アニタ・オデイ『オール・ザ・サッド・ヤング・メン』、『VOLUNTEERED SLAVERY』ローランド・カーク、『アット・ザ・ファイヴ・スポット vol.2』エリック・ドルフィー(SHM−CD)。
ディスクユニオン近くの天婦羅屋で天丼を食い、一路高円寺へ。午後2時から「座・高円寺」で芝居を観るのだ。遊園地再生事業団プロデュース『ヒネミの商人』。実は、ぼくが大好きな劇作家なのに、その演劇を生で一度も観たことがなかった宮沢章夫さんの初期の代表作が再演されると知ったからね。
------------------------------------------------------------------------
■「座・高円寺」という小屋は、なかなかに良いんじゃないか。ちょうど、松本市民芸術館「小ホール」の雰囲気によく似ている。キャパは300人くらいか?
始まった芝居『ヒネミの商人』に登場した宮川賢、ろくちゃん。彼を見ていて、誰かに似てるなあって、ずっと考えていたんだ。そしたら、ラストで流れたBGMを聴いて判った。小津安二郎『お早よう』みたいな音楽。あ、北竜二か。そうそう、あのいい加減さは、そうに違いない。
芝居『ヒネミの商人』は再演だ。もしかして、宮沢章夫演出の芝居が再演されたのは、今回が初めてなのかも。僕は初演を観ていない。でも、なんとなく判るよ。「劇的」であることを否定した芝居。時同じくして、平田オリザ氏も同じ地平を見ていた。でも、小津安二郎という方法論は同じでも全然違う。
ポイントは何なんだろう? 地図か? 貨幣か? 今は亡き街の記憶なのか? 確かに存在するはずの物語が、実は存在しない。ガラガラと崩れてゆく現実。その端緒は、銀行員「渡辺」の靴が片方だけ無くなったことから始まる。ところで、「ウルトラ」って何なんだ! 訳わかんないぞ!「ウルトラ」
-----------------------------------------------------------------
オリジナルは、シェークスピアの『ヴェニスの商人』だ。それは判った。だから、ユダヤ人の金貸しシャイロックは銀行員「渡辺」なのだな。ビット・コインみたいに、この世に存在しているようでいて、どこにもない貨幣の価値。それを代償する土地という神話。でも、連帯保証人の印鑑をひとたび押してしまったならば、先祖代々護り次いで来た「土地」を、いとも簡単に銀行は差し押さえに来るのだ。バブルが弾けた後とは、銀行が「そんな不良債権」をいっぱい抱えて四苦八苦していた時期だった。
そんな1990年代前半。そこに登場したのが『ヒネミの商人』(物語自体は1970年代の話だが)という芝居だったのだな。
■正直言って、芝居が唐突に終わってしまい、僕は途方に暮れた。何だったんだ? わからない。あの偽札の意味は? いつまで経っても目的地「サルタ石」にたどり着けない旅行者の彼女の苦悩。わからない。その彼女を目的地に導こうと努力する加藤の無駄な努力。わからない。ぜんぜんわからないぞ!
この「現実崩壊感」こそ、じつは大切なんじゃないかと思う。いままで信じて生きて来た、その確信が、あっという間に崩れ落ちてしまう瞬間を、たぶん僕らは「この芝居」を観ることで、再確認するのだ。
で、結局この芝居を観て最も印象に残った役者さんはというと、中村ゆうじ氏ではない。残念ながらね。じゃあ、誰? それはね、佐々木幸子さんさ。彼女の存在感はハンパなかった。凄いな!
--------------------------------------------------------------------
■「ヒネミの商人」。あとからジワジワとボディ・ブロウのように効いてきて、ずっと後を引く芝居だった。「面白かった!」と、単純に呟いていいのか戸惑うほど、個人的にものすごく衝撃的だったことは間違いない。それから、変なところが気になった。「全館禁煙」のはずの劇場で、主演の中村ゆうじ氏はステージ上で煙草をくわえ、当たり前に平然と火をつける。深く息を吸い込み、煙を吐き出す。ちょっと過剰すぎる煙が劇場内にたなびく。
でも、劇場の火災報知器は「その煙」を感知しない。不思議だ。(追記:演出上必要なシーンならば、役者が煙草ををふかすのは芝居では当たり前だったのですね。無知でした。すみません)
ぼくは禁煙して22年になるけれど、なんか久々にタバコを吸ってみたい誘惑に駆られたシーンでした。あーいう「タバコの吸い方」を、そういえば昔、ずいぶんとしていて、すっごく懐かしかったから。たぶん、宮沢章夫さんも現在は「禁煙」されているはずで、あの煙草に「郷愁」を込めたかったんじゃないだろうか?
--------------------------------------------------------------------
■2014年の3月末に観て、これだけショックだったのだから、1993年の初演時にはどれほど衝撃的だったことだろう。だって、主演女優2人が客席に「お尻」を向けて、バック・ステージの方向に平然と「セリフ」を喋るんだよ。
ただ、小津の映画ではそれは「当たり前」のことだ。映画『麦秋』では、原節子と三宅邦子の2人の女優が、その豊かな「お尻」を惜しげもなく正面から、スクリーンを見つめる観客に対して曝しているのだ。『東京物語』でもそう。宮沢章夫氏の演出では、確信的に「それ」を模倣する。
小津演出との類似は、たぶん「模倣」なのではなくて、結果的に「そうなってしまった」んだと思う。小津は、役者の「劇的な演技」を極端に嫌った。『秋刀魚の味』に出演した岩下志麻は、100回以上も繰り返し同じ演技をさせられたという。
ぼくは『ヒネミの商人』の芝居が始まって、役者さんがセリフをやり取りするのを聞き、すっごく心地よい感じがした。なんか、懐かしかったのだ。そう、小津安二郎の映画を観ているみたいでね。特に、ラーメンのくだり。人の会話って、唐突に関係ない方向に行ってしまったかと思うと、また戻ってくるのだ。
-----------------------------------------------------------------
■「劇的」という言葉は「西洋の演劇」と置き換えてもいいかもしれない。そこから最も遠い地平。それは「東洋」の代表的な演劇「能」だ。小津は「能」を映画に撮った『晩春』だ。劇作家、太田省吾は「転形劇場」で小町風伝を演出した。劇的を排した自然の演技を目指す究極は、能の様式美だ。
小津の映画は、そのローアングルで固定されたカメラからきっちりと幾何学的に構図された画面に役者を配置する。決して役者の勝手な演技は許さない。小津が自分で信じる「形式美・様式美」に反するからだ。
そういえば、『ヒネミの商人』の舞台装置も、実にシンプルで様式美を意識していたと思う。舞台後ろに「ふすま」の桟みたいな柱が並んでいて、印刷屋の中と外の道を隔てていた。外を歩く人はみな、転形劇場『水の駅』みたいなスローモーションの歩みをしていて可笑しかったな。
ふと思ったのだが、宮沢章夫氏は「歌舞伎」を演出するんじゃなくって、本来は「能」を演出するべき、なんじゃないかと。
「能」で重要なことは、「死者」が主人公となることだ。平家の幽霊とかね。存在しないはずの人が一人称で語りだす。ここが重要なのかもしれない。
-----------------------------------------------------------------
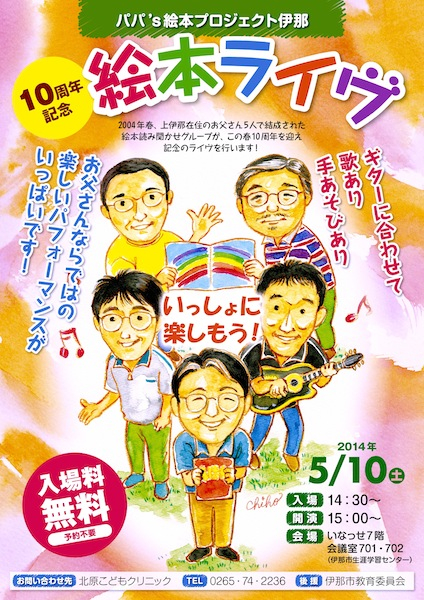


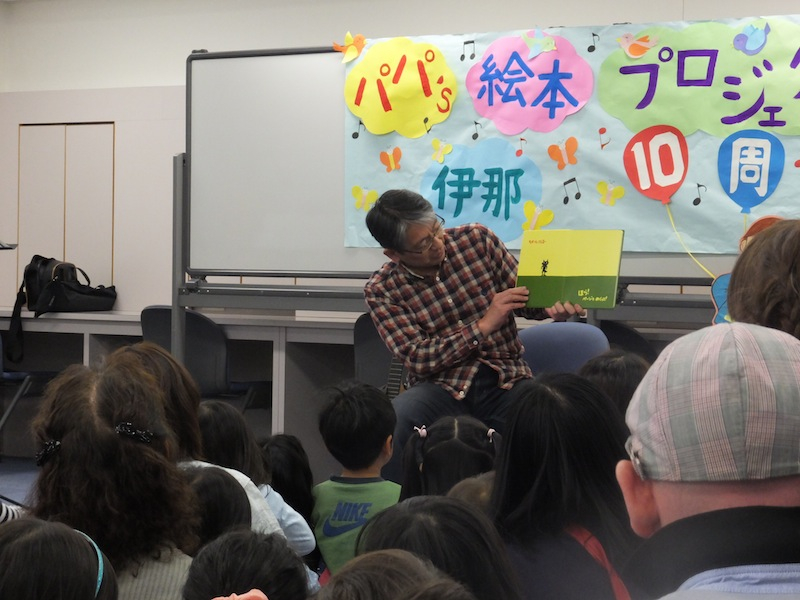


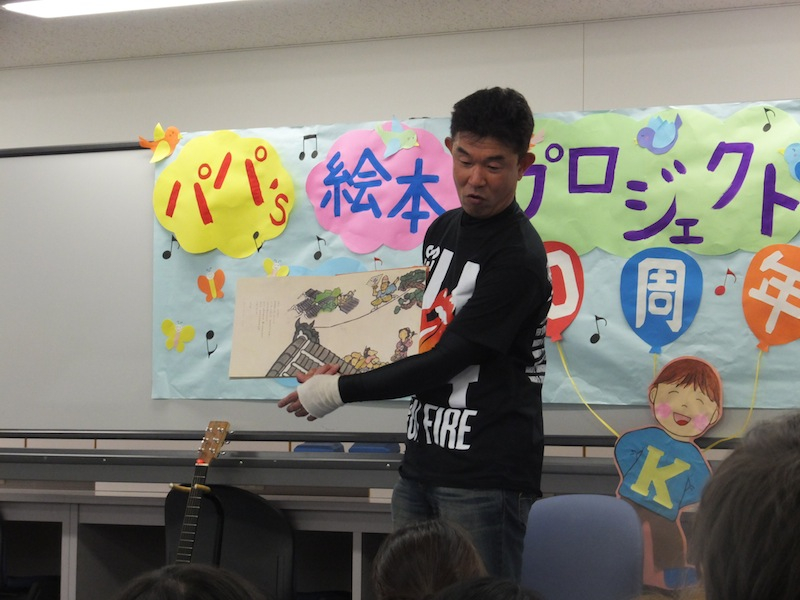











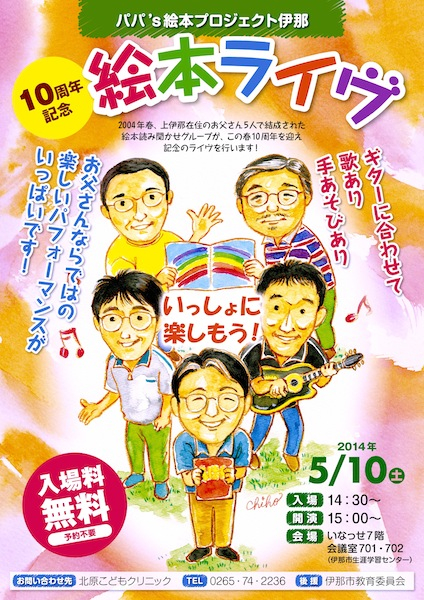
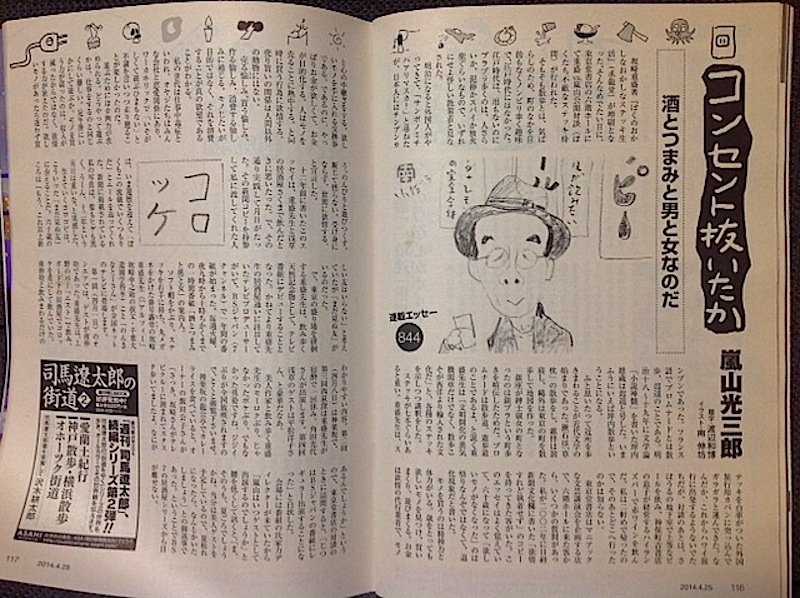
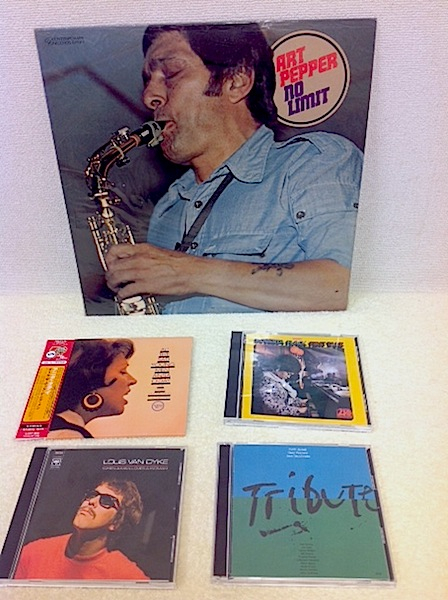


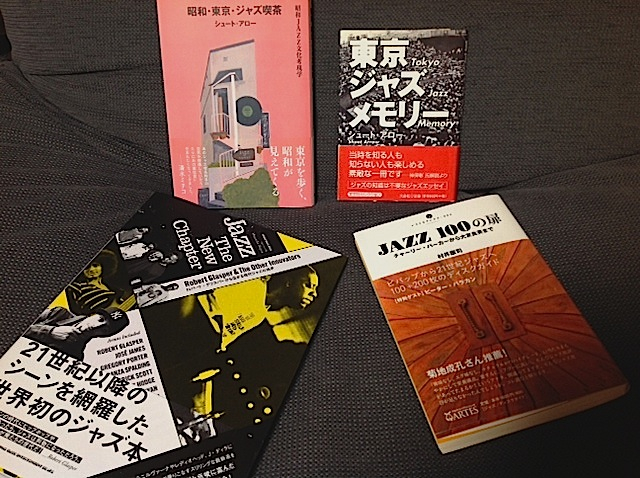
最近のコメント