『白鍵と黒鍵の間に』南博(小学館文庫) その2
■続きを書こうと思ったのだが、肝心の文庫本が行方不明だ。困ったぞ。ま、いいか。
この本を読んで僕がシンパシーを憶えるのは、主人公の南博氏にではなくて、彼の周囲で蠢く「ダメダメ人間たち」だ。
例えば、銀座のクラブで生演奏していた彼の上司のバンマスたち。終戦直後のドサクサに紛れて、米軍キャンプでのハワイアンのクラブ演奏を足がかりに、長い下積み生活を経てバブルの銀座で確固たる地位を築いた(と本人は思っている)バンマスたち。
音楽のプロフェッショナルなのに、誰一人ぜんぜん聴いてはいないクラブの空間で何十年も毎日来る日も来る日も演奏し続けてきた。そういうバンマスを、彼(南博氏)は一応は敬いながらもどこか軽蔑している。ぼくは、そんなくだりをを読みながら、しみじみ悲しくなるのだった。
まだ若い南氏が、ただただ日常を流しているだけにしか見えないバンマスを見る目は、ぼくが医者になって2年目に感じた、当時勤務していた総合病院の小児科部長に感じていた「不満」そのものだ。なんだ、この人は偉そうなこと言ったって、所詮は何の実
力もない「風邪しか診れない医者」じゃないか! ってね。
しばらくして、それはとんでもない間違いだったと未熟な僕は気付くことになるのだが、それはまた別のはなし。
で、あれから30年が経って、当時の小児科部長の年齢を超えた僕はしみじみ思うのだった。当時、偉そうにあぁ言ってた自分が「風邪しか診れない医者」そのものであるという現実を。それはそのまま、例の銀座のバンマスたちに重なるじゃないか。(ここで、白衣のポケットに入ったままになっていた文庫本を発見!)
当時の南博氏は、CMで急に有名になったハンク・モブレイの「リカード・ボサ・ノヴァ」を、連日何度もリクエストされて辟易したという。

YouTube: Hank Mobley - Recado Bossa Nova

YouTube: Eydie Gorme The Gift!(Recado Bossa Nova)
でも、それを嫌な顔ひとつせずに、その都度新鮮な気持ちで同じ曲を演奏するのが本当のプロなんじゃないか? ぼくはそう思うぞ。だって、開業小児科医の日常は、まさに「それ」だからだ。
下痢した子が来れば、どんな食べ物を与えたらいいか丁寧に話し、赤ちゃんが初めて高熱を出してあたふたしている若いお母さんに「心配しなくていいよ、おかあさん。最初の試練だけれど、これを乗り越えると、子育てのランクが一つ上がるからね、がんばって」と、昨日とまったく同じことを言っているぼくがいるのだよ。
南氏は「厭きる」と言った。でも、ぼくは厭きることはない。たぶん、彼の上司のバンマスも、そう思っているに違いない。ぼくはそう思うぞ。それを、アーティストとしての自らの誇りや向上心を放棄して、生ぬるいバブルの銀座で日々惰性だけで演奏しているから「厭きる」ことがないのだと南氏は考える。
だから彼は、このまま銀座でピアノを弾いていたら、ただただ腐って朽ちていくに違いないと感じたのだろう。
彼は、菊地成孔氏が盛んに引用する「バークリー・メソッド」で有名なジャズ・アカデミーの最高峰、ボストンにあるバークリー音楽大学への留学を決意するのだった。ボブ・マーリィの歌のタイトル通りの、まさにバブルの銀座ぬるま湯ダメダメ人生からの「エクソダス」だったワケだ。その圧倒的な決断力と実行力には素直に感服するしかないや。いや、凄い。
そういったリスペクトでもって、当時の銀座で蠢いていた人たちがちゃんと南氏の渡米を祝福するシーンが泣かせる。バンマス曽根さんの義理の兄で「そのスジ」の中堅格、このあたりのシマを取り仕切っている「兄貴」に、「やめさせてください。アメリカにいって勉強してみたいのです。僕にチャンスをください。」と、南氏は正直に告白する。それに対する「兄貴」の対応が泣かせるじゃないか!(p315〜317)
この場面は好きだな、いいなぁ。
なんだ、あーだこーだ文句を言いつつも、結局は著者の生き方にすっかり魅せられてしまったんじゃないか、ダメダメ人間の俺。
■ところで、ぼくは南博氏のピアノ演奏を生で一度だけ聴いたことがある。「ここ」の下の方にスクロールしていくと「森山威男カルテット・ハッシャバイ」の項目があるが、その終わりのあたりに、1996年の夏の終わりに、長野県富士見高原スキー場で行われたジャズ・フェスティバルのことが書いてある。南博さんの「プロフィール」を見ると、1996年、南博QUARTET にて、八ヶ岳 THE PARTY PARTY に出演。とあるのがそれだ。
新宿ピットインのマネジャーを長く務めた龍野さんが、故郷の山梨県に帰ってから始めたジャズ・フェスの、富士見町に場所を変えての一回目だったと思う。当時ぼくは、富士見高原病院小児科の一人医長だった。
ただ思い返すに、ゲスト・ヴォーカルで登場した「綾戸智絵」のパフォーマンスがあまりに凄すぎて、南博氏のピアノがオーソドックスで端正なピアノだったことしか印象に残っていないのだ。ごめんなさいね。CDでは、菊地成孔氏とのデュオ演奏が納められた『花と水』を持ってて、深夜しみじみ落ち着きたい時なんかに、時々聴いてるよ。
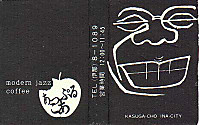
最近のコメント