『聴いたら危険! ジャズ入門』田中啓文(その2)
■本当は、オイラみたいなすれっからしのジャズファンが「この本」のことをどんなに誉めてみたところで、実はあまり意味はないんじゃないかと思ってしまうのだ。
だから、まったくのジャズ素人なのに「ジャズ入門」のタイトルに騙されて、間違って「この本」を買ってしまい、なんか面白そうじゃん! とさらに勘違いして、amazonで、ブロッツマンとか、ファラオ・サンダースとか、ローランド・カークとかの「著者オススメCD」を思わずポチッてしまい、送られてきたCDを何とはなしに聴いてみたら「案外いいじゃん!」と、その後どんどんフリー・ジャズの世界にのめり込んでしまいました!
っていうような感想を、著者の田中啓文氏は読みたかったんじゃないかな。
ただ、なかなかそれは難しいことだとは思うのだけれども、「へぇ〜、こんなのもジャズなんだ!」って興味を持ってくれる人は「この本」のおかげでずいぶん増えるんじゃないか。
■何なんだろうなぁ。とにかく、ぼくは田中啓文氏が書く小説が好きなのだ。
『落下する緑―永見緋太郎の事件簿』シリーズも、『笑酔亭梅寿謎解噺』シリーズも、ハードカバーで買って読んでいる。著者は、基本超マジメなのに、変に無理してサービス精神が旺盛すぎるのだ。
だから「この本」でも、変に読者に受けを狙いにいったミュージシャンの項目(ファラオ・サンダースとか、ジュゼッピ・ローガン、アーチ・シェップなど、ぼくも大笑いしたが……)よりも、真摯に真面目に書いている項目のほうが読み応えがある。例えば「アルバート・アイラー」の文章。
なんといっても、あの「音」である。朗々と鳴り響く、管楽器を吹く原始的な喜びにあふれた野太い、輝きに満ちた音。あれを聴くだけでも、彼の音楽の根源にあるものが何かわかるではないか。それ以外にも「ガーッ!」という割れた音、口のなかの容積を変化させることで得られる歪んだ音、しゃくりあげるように裏返っていくフラジオ、グロウルによるダーティーな音などを効果的に使っているアイラーは、サックスから獣の大腿骨を楽器がわりに吹いていた頃のような原初の音を引きずり出す。(p48)
これほど、アイラーの音色の本質に迫った文章を、ぼくは今まで読んだことがなかった。すごいぞ。
あとはそうだなぁ、エヴァン・パーカーの項。
パーカーは、「こういう音が出したい」「こういう演奏がしたい」というところからはじめて、自分の楽器をじっくり見つめ、そしてこうした技法にたどり着いたにちがいない。(中略)なにしろ、サックスで世界で初めてこんなことを成し遂げたひとなのである。歴史の教科書に載ってもいいぐらいの偉人である。(中略)パーカーのソロにはある時期救われたことがある。会社務めが合わなかった私は、昼休みは食事もせずにCDウォークマンでずってこのアルバムを聴いていた。鬱陶しい現実の世界から浮遊できるひとときを、彼のソロは毎日あっという間に作り出してくれた。(p81)
この傾向は、日本人ミュージシャンの項目で顕著となる。
富樫雅彦、坂田明、阿部薫、林栄一、梅津和時、高柳昌行、大友良英、明田川荘之、片山広明などのパートを読むと、著者の真面目さが際立っているように思うぞ。
ぼくが特に注目したのが「阿部薫」だ。
阿部薫のように「情念」に任せた即興は、空虚でひとりよがりなものになりがちだが、彼の演奏はそうではない。その理由は「間」と「音」にあると思う。阿部のソロは「間」が多い。ひとりで吹いているのだから当然、と思うかもしれないが、プレイヤーは無音状態を嫌うもので、それを埋めたくなる。エヴァン・パーカー、カン・テーファン、ミッシェル・ドネダなどが循環呼吸とハーモニクスによって途切れなく、空間を音で埋め尽くしているのに比べ、阿部のソロは、静寂が延々と続き、これで終わり?と思った頃に、ぺ……と音が鳴ったりする。常人なら耐え難い長尺の静寂をあえて選択し、無音と無音を組み合わせて、あいだに音を挟んでいく。ここまで大胆に静寂を押し出した即興演奏家はいなかった。(p142)
ぼくも阿部薫の『なしくずしの死』が大好きなのだが、彼の「無音の魅力」には気が付かなかったな、まったく。さすがだ。
田中氏が書いた文章は、どれもこれも「そのミュージシャン」に対する「ひたむきで敬虔な愛とリスペクト」に満ちている。それが、読んでいて実にすがすがしいのだ。
だから逆に、田中氏以外の人が書いた文章が妙に浮いてしまっている。これらはいらなかったんじゃないか? 田中氏だけの文章で埋め尽くせばよかったのに、何故だ? たぶん、自信がなかったのだろう。だからあのまどろっこしい、言い訳がましい「はじめに」と「おわりに」になってしまったのではないか。
そんなこと言わなくてもいいのになぁ。
後半に載っている、カヒール・エルサバー、ハミッド・ドレイク、ポール・ニルセン・ラヴ、芳垣安洋、大原裕とかは、ぼくも「この本」で初めて知った。どんな音を出すのか、ぜひ聴いてみたいぞ。

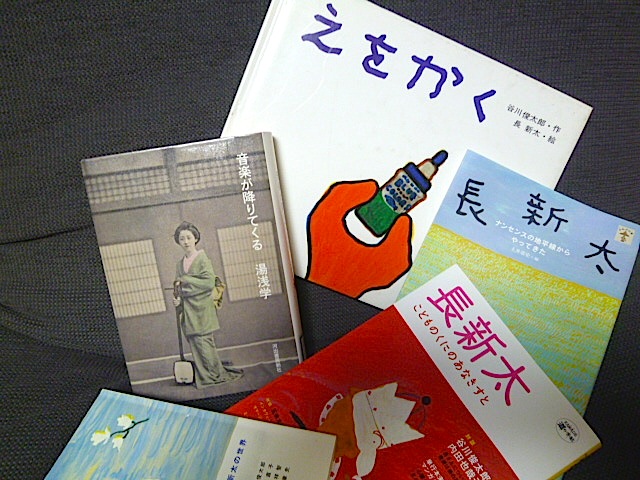
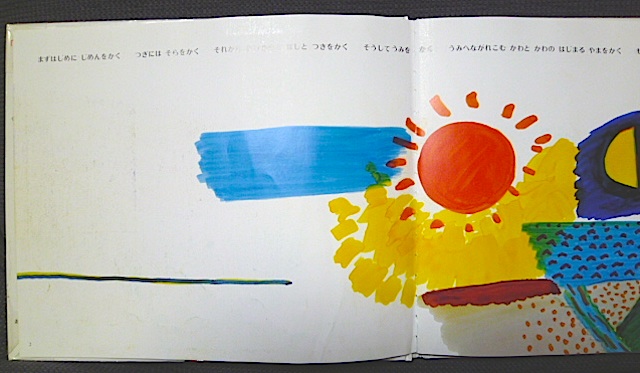
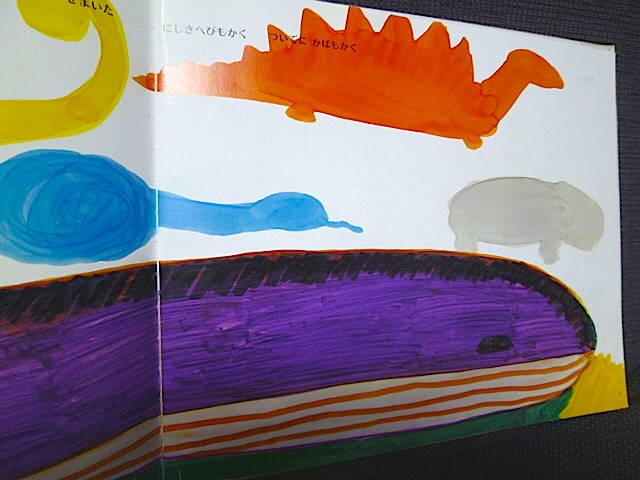
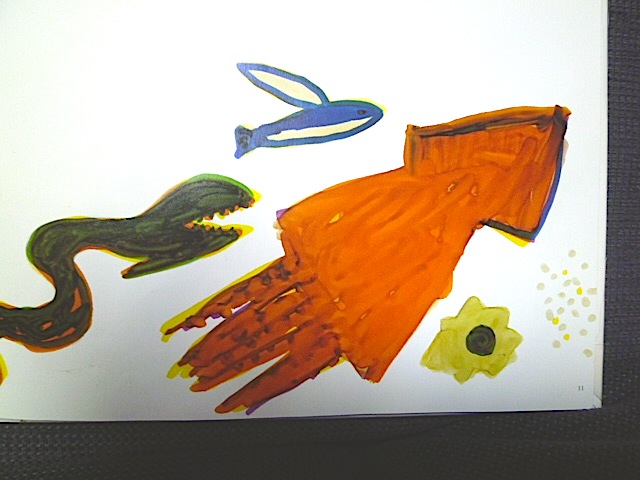
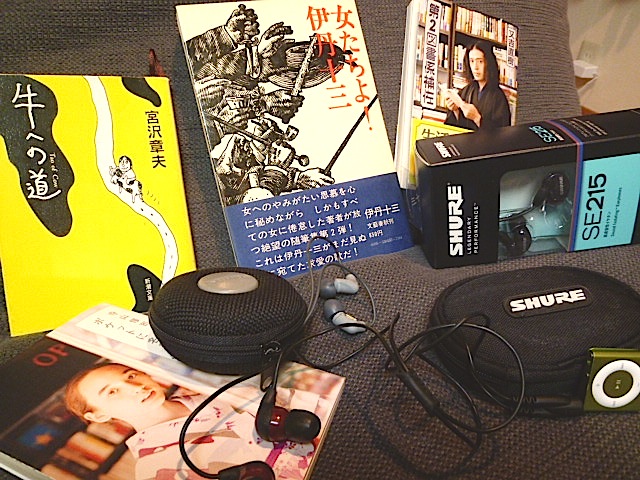

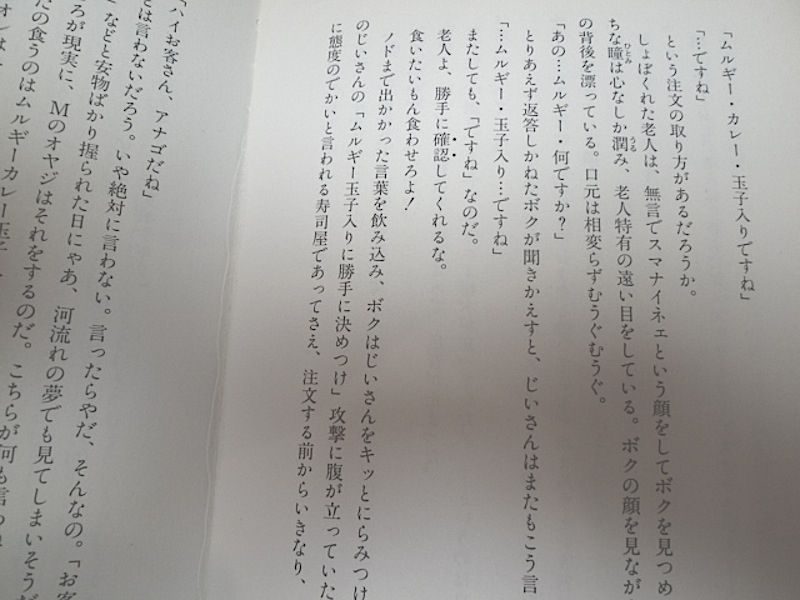


最近のコメント