『ジャズ喫茶論 戦後の日本文化を歩く』マイク・モラスキー(筑摩書房)その2
■先ほど読了した。この本はほんと面白かったなぁ。
普通、ジャズ喫茶の話となると、昔はよかったなぁっていう、単なるノスタルジーだけで語られた本がほとんどだったのに、この本は違った。第一に、著者が変な外人(セントルイス生まれのアメリカ人)で、しかも、一橋大学社会学研究科教授の肩書きで「日本語」で書かれた本である、ということが驚きだ。彼の書く日本語がじつによくこなれていて読み易いのだ。
第二に、各ジャズ喫茶が自慢するオーディオ・スペックや、ジャズレコード・コレクションを記載することを、意識的に排除したこと。これが意外だった。当時、ジャズ喫茶のスピーカーは「JBL派」と「アルティック派」とに分かれていた。それぞれの代表が、岩手県一関市の「ベイシー」と、東京は門前中町にあった「タカノ」だ。もちろん、この本には日本のジャズ喫茶のメッカであった、この2つの名店の記載はある。「タカノ」はマッチの写真も載っている。でも、著者は微妙に外して紹介しているのだ。そこに、モラスキー氏のポリシーを感じて面白かった。
第三に、著者が「ジャズ喫茶」体験をした時期と、ぼくが「ジャズ喫茶」体験をした時期とが、ぴったし一致すること。本書264ページによると、それは「ジャズ喫茶混迷期 --- 1973年頃〜1980年代初頭」に当たる。巻末に載っている、著者が全国旅して取材した各地の「ジャズ喫茶」リストを見ると、ぼくが大学生の頃に日本全国を旅して巡って実際に訪れた「ジャズ喫茶」が25店以上もあった(現在は営業していない店も含めると)。あのころ集めた「ジャズ喫茶のマッチ」を、たしか今でも取ってあったはずなのだが、納戸の奥の段ボール箱の中に仕舞われているみたいで、発見できなかった。残念。
■ぼくは「Web ちくま」に著者の連載が載ったときから、ずっと楽しみに読んできたのだが、1冊の本になって読み返してみると、実に見事に再構成されていて、すごく読み易くなっていることに感心した。
それから、読みながら「はっ!」とさせられる記載が随所にあったことも注目に値する。たとえば、
そして、あまり指摘されないようだが、ジャズ喫茶の店主たちの中に、社会の主流的価値体系に抵抗心は抱いていても、闘争や組織などに直接関わったりする人が少なかったように思える。つまり、個人レベルでは大まかな「反体制精神」は共有していても、基本的に「ノンポリ」の店主が圧倒的だった、ということは見逃せない。(p263)
たしかに、かつてジャズ喫茶の店主でもあった村上春樹は、まさにそうだった。
基本的には店主がレコードを棚から選択し、ジャケットから盤を取り出し、ほこりをきれいに拭き落とし、ターンテーブルに置く前に表面の針の傷の有無を点検し、そしてターンテーブルに置いてから位置を慎重に定めながら針を落とす。どの行為もきわめて慎重に行われ、見ている客には、レコードとオーディオ装置の希少性が十分に伝わり、同時に店主自身のジャズに対する知識と愛情が披露される結末になる。私はこれらの行為を<パフォーマンス>と見なしたい。いわば、<通の演技>である。あるいは、演奏するという不在のミュージシャンの代理行為とでも見なせるかもしれない。(中略)
ところで、LPに対するフェティシズムはあっても、CDに対するそのような態度をジャズ喫茶ではほとんど見かけない。(中略)
ジャズ喫茶でCDがヒンシュクを買っているとしたら、その理由は単に音質や上記の具象性をめぐる問題だけに由来するのではないような気がする。店内の秩序を乱し、しかも店主や店員のパフォーマンス的表現の大事な一部を奪ってしまう、という効果も関係しているのではないかと思う。
■この本が、単なるノスタルジーに終わらない店を挙げるとしたら、
1)アメリカ軍基地がある街には「ジャズ喫茶」が数多く存在するに違いない、ということにこだわっているところ。彼はそのために沖縄を何度も訪問している。これは、日本のジャズに言及した評論の中で、欠落していた視点だと思った。
2)地方の、一般にはほとんど知られていない「ジャズ喫茶」にスポットを当てた功績は大きいな。特に、北海道は函館の「バップ」(ここは僕も行ったことがある)とか、海のない埼玉県にある「海」という名のジャズ喫茶とか。あとは、大阪阿倍野区(たぶん飛田遊郭の近く)にあった「マントヒヒ」や、若松プロダクションに所属していたマスターの店「ろくでなし」の紹介。
それから、熱海の遊郭街の外れで細々と営業を続ける「ゆしま」とか。常連は、結婚してもいい相手かどうか、ゆしまのママに鑑定してもらっていたという。
あとは、ジャズ喫茶といえば昔から敵対関係にあった「JASRAC」の著作権に対する取り立ての話も面白かった。断固許さず対決して裁判で負けた、新潟「スワン」のマスターの話をもっと聴きたいぞ。
3)著者は「ジャズ喫茶」を決して「過去の遺産」もしくは「博物館」としてノスタルジックに懐古しているのではなくて、新しいタイプの「ジャズ喫茶」に期待している記述があること。
その、新しいタイプのジャズ喫茶とは、沖縄県ゴザにできた「スコット・ラファロ」と、井の頭公園の脇のビル7階にできた「ズミ」だ。それから、大阪にできた古本屋&ジャズ・カフェの「ワイルド・バンチ」も期待できるか。
4)日本人が、よくジャズを分類する時に使う「しろ(白人)」「くろ(黒人)」の表記はナンセンス! と著者が声高に主張している点。これは気付かなかったな。なるほど。ぼくも知らずとそういう分類をしたきたような気がする。女性ジャズ・ヴォーカルなら、やっぱり白人金髪とか。動機が不純だね。
5)ジャズ本来の楽しみ方である「ライヴ」と、ジャズ喫茶で再生される「レコード」での「ライヴ録音」の関係。その「リアルさ」を競うこと。それはそのまま、落語の再生記録は、DVDで見てもちっとも「リアル」には感じられないのに、CD(もしくはレコード)の音だけで目を閉じて聴けば、リアルな寄席の空間が体感できることと同じだ。
(もう少し続くかも)
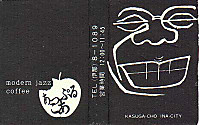







最近のコメント