『きみの鳥はうたえる』佐藤泰志(河出文庫)読了
■佐藤泰志氏は、昭和24年(1949年)4月26日函館生まれだ。いま生きていれば、62歳か。ぼくの兄貴と同い年だな。あと作家では、村上春樹、桐山襲、北村薫、亀和田武らがいる。矢作俊彦、内田樹、平川克美、高橋源一郎、中沢新一は、ひとつ下の学年になるようだ。いわゆる団塊世代では「少し遅れてきた青年」に属するのか。
■『きみの鳥はうたえる』(河出文庫)に収録された『草の響き』(1979)は、なんと「ランニング小説」だった。私小説とまでは言えないかもしれないけれど、著者の実体験をもとにしているらしいことが、文章を読みながらリアルに感じられる。
長距離ランナーとしても有名な同い年の作家(早生まれだから学年は一つ上)村上春樹氏が走り始めたのは、1982年の秋のことだ。ジャズ喫茶のマスターを辞めて、タバコも止めて、専業作家となる決意をして千葉に引っ越し、代表作『羊をめぐる冒険』を書き始めた頃のこと。村上氏は言う。当時まだジョギングはマイナーなスポーツで、皇居の周りを走る人もあまり多くはなかったようだ。
でも、佐藤泰志氏が走り始めたのはもっと古くて、1977年の春だった。この「年譜」によると、当時彼は28歳で、書店務めのあと、日本共産党の機関誌を印刷する「あかつき印刷」に就職するも、精神の危機的不調に陥るのだった。この頃の話が、小説『草の響き』となっているようだ。当時通っていた精神科の医者に「ランニング」を薦められ、佐藤氏は走り始める。住んでいた八王子の都営団地からほど近い「大正天皇陵」まで、雨の日も暑い夏の朝も、毎日毎日走り続けるのだった。
根が真面目だから、彼は黙々と走り続ける。まるで、シリトー『長距離ランナーの孤独』みたいに。走り始めた当初は、1.8km を13分強で走っていたのが、いつしか5キロを20分で走れるようになって、連日10km以上走ることが日課となっていったという。
小説『草の響き』の中で、ぼくが一番好きな場面は p184〜p191の、暴走族との出会いのシーンだ。淡々と走る主人公に無理して粋がって併走しようとする少年たち。BGMで「ユー・キャント・キャッチ・ミー」が彼らのラジカセから流れている。実際、彼について行ける者はほとんどいなかった。暴走族のリーダー「ノッポ」を除いて。
主人公と彼とはほとんど口をきかない。しかし、いっしょに走り終わったあと二人黙ってタバコを吸い合えば、言葉はなくとも全て分かり合える気がした。読んでいて羨ましいなって思った。正直。
村上春樹氏は、自作の中でランニングに関して語ることはほとんどない。でも、ぼくには『草の響き』の主人公が何故走るのか、痛いほど切実に伝わってくるのだ。そうだ、そうだよ! ぼくもおんなじさ。
足に力をこめて踏みだすと、ふくらはぎの筋肉がすばやく伸縮する。振り出しに戻るのはまっぴらだ。僕はこのまま走るだろう。(p224)
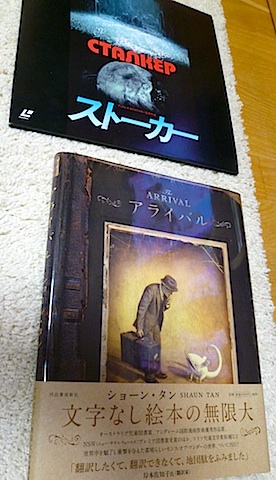

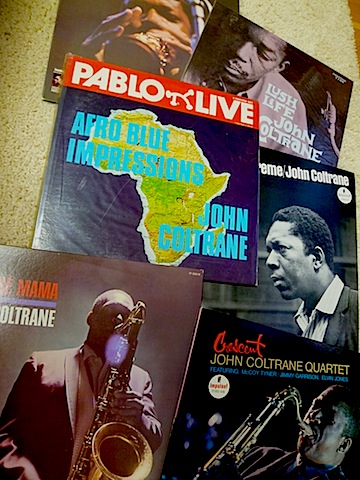
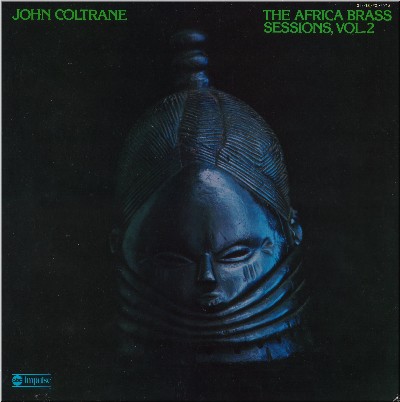







最近のコメント