『あまちゃん』の夏が終わろうとしている。
■大阪のFMラジオ「FM80.2 BINTAN GARDEN あまちゃん特番」前編・後編で放送された、宮藤官九郎ロング・インタビューが聴き所満載で、ちょっと驚く。クドカン、よく喋るなぁ。YouTube にアップされた前編、後編それぞれの後半30分が宮藤官九郎のインタビューに割かれている。
なお、前編では「ピエール瀧」が、後編では「マキタスポーツ」が、出演者としてコメントしていて、これまたなかなかに面白い。

YouTube: あまちゃん 特番 FM80.2 BINTAN GARDEN 前編 あまちゃんナイト~おら、このままじゃ終われねぇ!じぇじぇじぇギョギョギョな1時間!

YouTube: あまちゃん 特番 FM80.2 BINTAN GARDEN 後編 あまちゃんナイト~おら、このままじゃ終われねぇ!じぇじぇじぇギョギョギョな1時間!
■『TV Bros. / 9.14〜9.27』の、「あまちゃん」総力特集! の力の入り方が尋常じゃない。読みどころ満載だ。
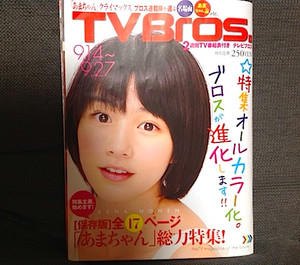
見開き4ページに渡って載っている、大友良英&細馬宏通・対談【音楽から考える「あまちゃん」と、「あまちゃん」から考える音楽。】が、何と言っても一番の注目記事だが、こちらの「オリジナル音源」を「大友良英 JAMJAMラジオ」で聴くことができる。
細馬宏通さんのブログで、少し前に書かれていたことに、『TV Bros.』に載った、井上剛チーフディレクター・インタビューの後半に出てくる、1シーン撮るのにカメラ5台を同時に回して、さらにカメラ・ポジションを変えて同じシーンを撮るという話。
今週火曜日の「腹黒ユイちゃん完全復活のシーン」は、なるほどそうやって撮ってるからテンポよく、ビビッドに視聴者に伝わるんだ! と、しみじみ思った。
それにしても、この回の「あまちゃん」はよかったなぁ。本放送4回(BSで2回、地上波で2回)と、録画で2回(息子たちといっしょに)見た。そうそう、ここ。ここがよかったなぁ。ストーブさんと勉さんが、じつにいい仕事をしている。
「やりたいよ!……やんないよ!でもやんないよ」「やりなよ」「やればいいのに」「やんないよ」「やれよ!」「やるよ!」「やったーーー!」
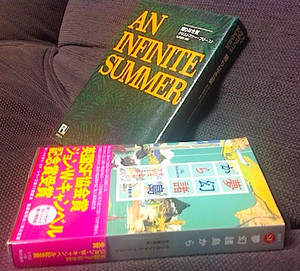
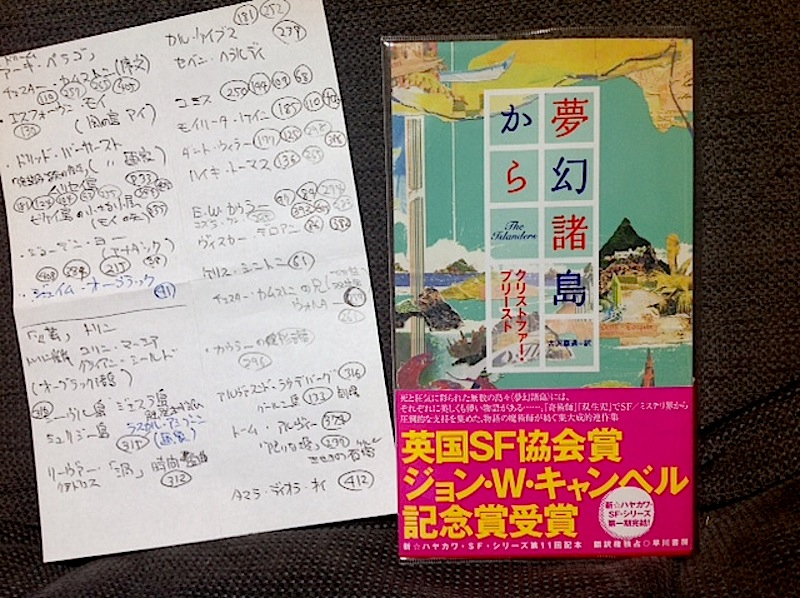
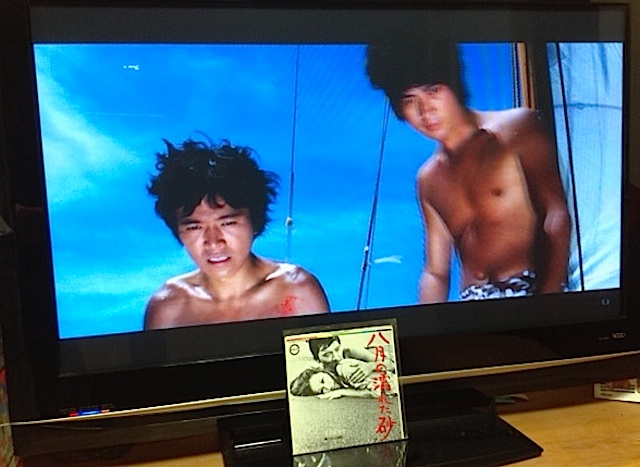

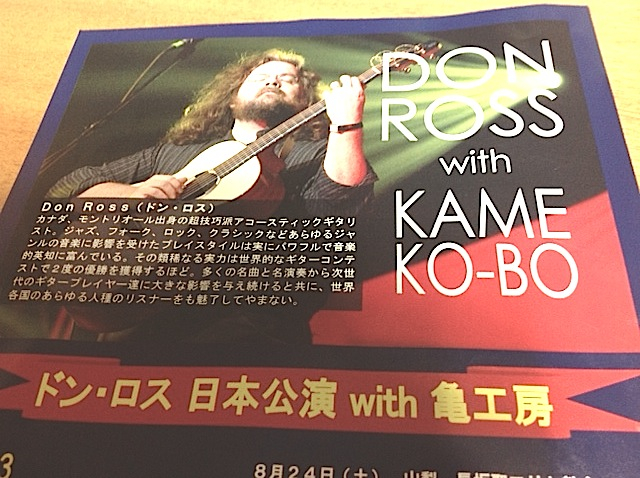
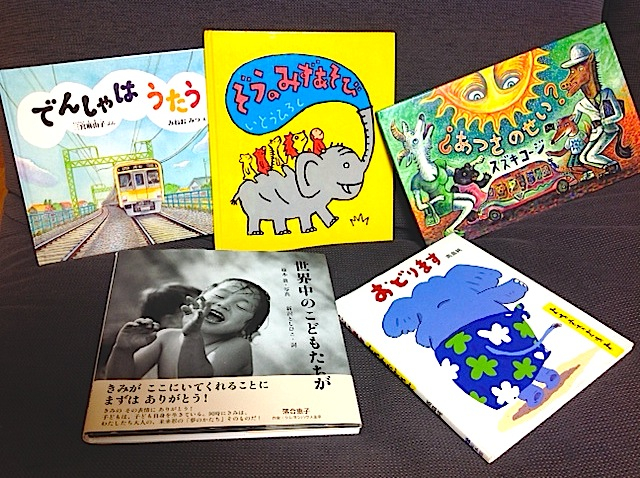







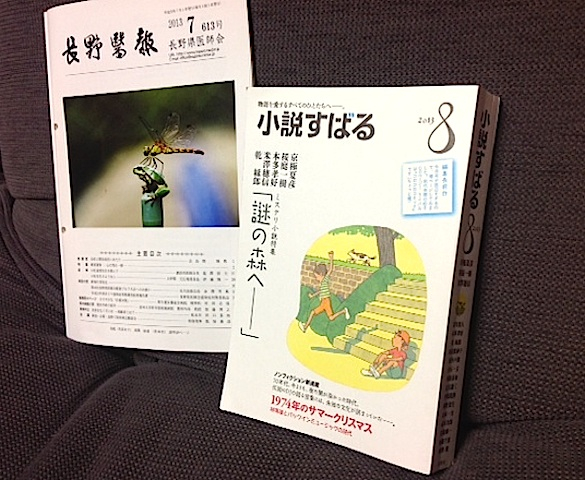
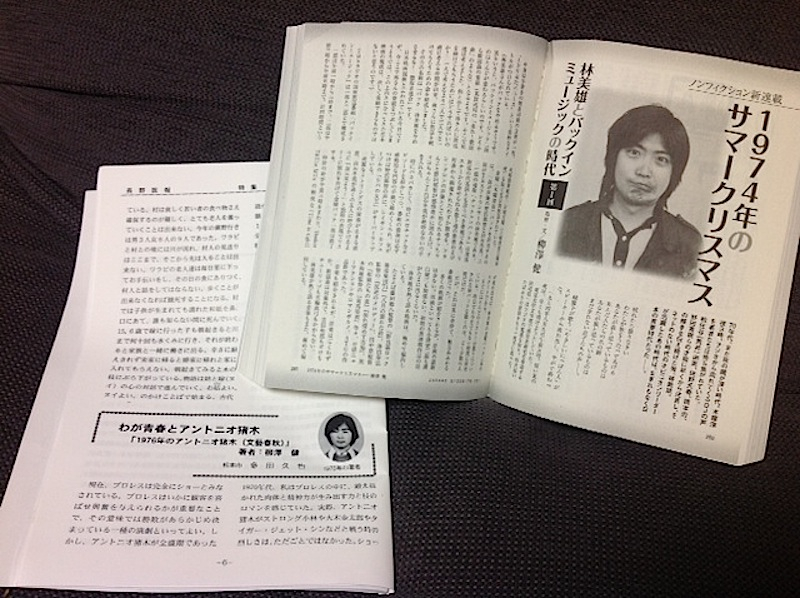
最近のコメント