同じ年生まれの人が気になるのだ
■『「当事者」の時代』佐々木俊尚(光文社新書)を読み終わった。
新書にしては、ずいぶんと分厚い本だったが、途中で厭きることなく一気に読めた。すっごく面白かったからだ。
著者は元毎日新聞社会部記者で、なぜ記者を辞めてしまったのかは、こちらの「糸井重里さんとの対談」に載っている。そうだったのか。ぜんぜん知らなかった。
この本の最初の2章は、著者が新聞記者だった時の実体験が描かれていて、これがじつに面白い。夜討ち朝駆けとはまさに新聞記者の日常なのだな。小説とかテレビドラマとか映画で見る、特ダネ記事を狙う新聞記者そのものじゃないですか。でも、この本を読んで初めて知ったのは、その花形新聞記者たちの赤裸々な心の内だった。なるほどなぁ。
この第2章〜第4章は、1960年代末から1970年代初頭にかけての大学紛争と、その思想的バックボーン。その栄光と挫折の歴史が分かり易く書かれていて、この本の読みどころとなっている。
ところで、著者の佐々木俊尚氏は 1961年生まれ。僕が 1958年生まれだから、連合赤軍の浅間山荘事件まで含めても、当時の事柄をリアルタイムで切実に記憶している世代ではないはずだ。なのに、何なんだ!? このリアルな描写は。
■僕が高校生だった頃は、本多勝一はまだ、朝日新聞のスター記者だった。
僕は読まなかったが、たしか、同級生のA君が『ニューギニア高地人』とかを、担任の先生から借りて読んでいたように思う。でも僕だって小田実の『何でも見てやろう』は読んだし、埴谷雄高や高橋和巳は読んで少しは分かった気がしたが、吉本隆明の『共同幻想論』はぜんぜん歯が立たなかったな。で探してみたら、いまわが家の書庫にある本多勝一(飯田市出身)の本は1冊のみ。『日本語の作文技術 』(朝日文庫) だ。でも、この本すらちゃんと読んでない。ごめんなさい。
■今年54歳になる僕でさえそんなんだから、いまの若者は「本多勝一って誰? 小田実って何者?」って感じなんじゃないかな?
今日、テルメで5キロ走った後に寄った「ブックオフ」で、『一九七二』坪内祐三(文春文庫)を見つけて買ってきた。1970年の大阪万博を小6の時に見に行った僕は、この年、中学2年生だった。ところで、坪内祐三氏は僕と同じ1958年(昭和33年)生まれだ。この翌年に山口百恵がブレイクし、森昌子、桜田淳子、山口百恵(昭和34年早生まれ)の「中3トリオ」が誕生する。
面白いことに、坪内祐三氏は以前から「同い年生まれの有名人」に異様にこだわる人だった。で、それが高じて『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り―漱石・外骨・熊楠・露伴・子規・紅葉・緑雨とその時代』 (新潮文庫) が生まれることになる。
■その他、「昭和33年(1958年)生まれ」の僕が気になる人には、例えばこんな人がいる。
・森岡正博(大阪府立大学人間社会学部教授)
・マイケル・ジャクソン
・マドンナ
・プリンス
・原辰徳
・鴻上尚史
・山田五郎
・中村正人(ドリカム)
・東 雅夫 (幻想小説愛好家)
・穂積ペペ(確か捕まったのでは?)
・永江 朗 (ライター)
・久保田早紀(異邦人)
・西川峰子
・伊藤咲子(ひまわり娘)
・吉野仁(書評家)
・岡田斗司夫
・大塚英志
・大澤昌幸
・武田徹
・久本雅美
・久住昌之(漫画家)
・ウォン=カーウァイ 〈王 家衛〉(映画監督)
・高泉淳子(女優)
・業田良家(漫画家)
・サエキ けんぞう
・日垣 隆
・宮下一郎
・江川紹子
・陣内孝則(俳優)
・日比野克彦
・阪本順治(映画監督)
・喜国雅彦(漫画家・古本愛好家)
・ジョン・カビラ
・岩崎宏美
・安藤優子
・小室哲哉
・宮崎美子
・樋口可南子
・早乙女愛
■1959年の早生まれの人は、山口百恵の他に、
・藤沢 周(作家)
・ダンカン
・シャーデー
・京本政樹
・北野 誠
・小西康陽
・岡田奈々
・吉野朔実(漫画家)
・飯田譲治
・宮台真司
・大月隆寛
・マキ上田(ビューティ・ペア)
・やく みつる
・嘉門達夫
・原田宗典
などなど。けっこういるなぁ。
■こういう過去の記憶をお互いに懐かしむ「世代論」は、たぶんこの著者が最も嫌う事項なんじゃないかと思うのだが、でも、たぶん「この本」を読む読者にとっては重要なポイントとなるように感じた。
あと、僕より 8〜9 歳年上の、1950年、1949年生まれの人たちに結構キーマンとなる人がいるような気がする。
彼らは、あの「1968年」年に、まだ18歳ないしは、19歳だったのだ。
彼らは団塊世代にくくられるのだが、ちょっとだけ「遅れてきた青年」だったのではないか?
・山田正紀 1950/01/16
・伊集院静 1950/02/09
・志村けん 1950/02/20
・カレン・カーペンター 1950/03/02
・佐々木譲 1950/03/16
・和田アキ子1950/04/10
・友部正人 1950/05/25
・中沢新一 1950/05/28
・矢作俊彦 1950/07/18
・池上 彰 1950/08/09
・内田 樹 1950/09/30
・平川克美 1950/07/19
・高橋源一郎1951/01/01
・大滝詠一 1948/07/28
・糸井重里 1948/11/10
・村上春樹 1949/01/12
・佐藤泰志 1949/04/26
・鹿島茂 1949/11/30
・関川夏央 1949/11/25
・亀和田武 1949/01/30
・大竹まこと1949/05/22
・松田優作 1949/09/21





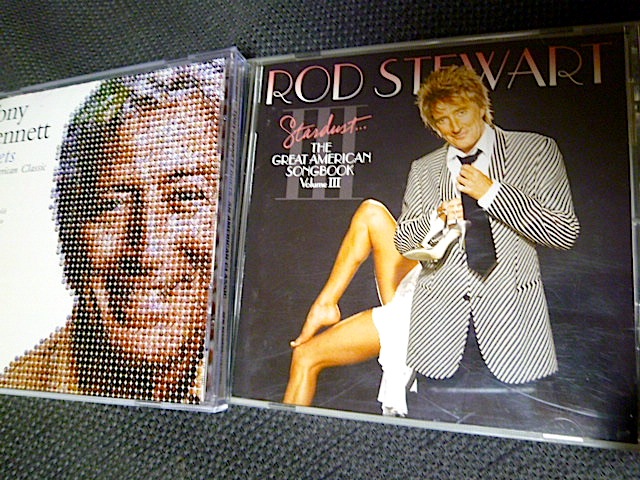

最近のコメント