ラジオを聴いていて、個人的関心事項がいきなりシンクロした瞬間がうれしい。『All The Joy』Moonchild
YouTube: Moonchild - 'All The Joy' (Official Video)
・
■GWは、4月30日(日)に守屋山(1651m)を登りに行った。初めて登ったんだ。今年は近くの里山登山をすることに決めていて、守屋山は、その第一弾というワケだ。高遠町片倉を超えて立石登山口より登攀開始。国道右側に駐車場があって、アクセスは抜群だ。巨石群を巡りながら、1時間10分で頂上に到達。疲れた。汗ビッショリ。でも、山頂からは 360度の展望が望めるのだ。これには感動したな。
写真は、守屋山山頂からの南側の眺め。左端は仙丈ヶ岳(3033m)、真ん中に北岳(3193m)、右側は間ノ岳(3189.5m)。さらに右には塩見岳(3047m)が連なる。
・
写真をクリックすると、もう少し大きくなります
・
■登山口まで車で乗り付ける途中に聴いてきた FMカー・ラジオから、久々に聴いたのが、土岐麻子『TOKI CHIC RADIO /トキシック・ラジオ』だ。子供が小学生だった頃は、日曜日といえば毎週朝から車で外出していたから、土岐麻子のこの番組(2009年10月放送開始。FM長野では、毎週日曜日の朝9:30〜。地方局のみの放送で、収録している東京FMでは何故か放送されていない)は以前はよく聴いていたのだ。
この日の特集は「G・W・ニコル」GW特別「いやし空間特集」だった。
で、土岐麻子さんが選曲してFMラジオで流したのが、この曲「All The Joy」Moonchild だったのだ。車で聴きながら「あっ! この曲知ってる。CDでさんざん聴いたぞ」と思ったのだが、その日は「どのCD」で聴いたのか、よく思い出せなかった。
写真をクリックすると、もう少し大きくなります
<写真をクリックすると、もう少し大きくなります>
・
■で、暫くして思い出したのがこのCD。『フリー・ソウル〜2010s・アーバンジャム』の、17曲目だ。去年はさんざん聴いてきたCD。「この曲」は、聴きながら「土岐麻子みたいなヴォーカルだなぁ」って思っていたんだよ。土岐さん自身もそう思ったのかなぁ。不思議なシンクロ。なんだか嬉しくなったんだ。
このCDには、ジャネット・ジャクソンをはじめ、エリカ・バドゥ、コリーヌ・ベイリー・レイなど、ネオ・ソウル界ベテラン女性歌手の新譜が収録されていることに加え、ルーマーとか KING とか要注目の新人も多数ピックアップされている。Moonchildも、そんな一つだった。
・
■ラジオといえば、5月4日(木)の午前中、NHKラジオ第一『すっぴん!』が渋谷で公開放送していて、金曜日レギュラーの高橋源一郎氏と、月曜日レギュラーの宮沢章夫氏が「大人の恋」をテーマに、それぞれ「オススメの一冊」を紹介し合っていて(ビブリオバトルの感じで)面白かった。
演出家である宮沢さんは、チェーホフの『三人姉妹』を、離婚を繰り返し、幾多の修羅場を経験されてきた高橋源一郎さんは、島尾敏雄『死の棘』。なんか、笑ってしまったよ。
・
さらに、5月5日(金)の夕方、外出先からわが家に帰って来て、たまたまラジオを付けたら、同じくNHKラジオ第一で放送していた「なぎら健壱のフォーク大集会」の終盤だけ聴くことができたんだよ。今回は「著名人リクエストアワー!」と題した有名人限定のリクエスト特集で、サイト内の「セットリスト」に載っている曲が、それぞれ有名人からのリクエストで順次流れたようだ。
ぼくが聴いたのは、その一番最後の宮沢章夫さんのリクエスト。候補曲を何曲か挙げていて、ディランII、斉藤哲夫「悩み多きものよ」、加川良はあったっけ? それから、友部正人の「あいてるドアから失礼しますよ」。
宮沢さんは「この曲」の主人公はいま「そのドア」から部屋の中へ入ってくるところなのか、それとも、たったいま部屋から出て行くところなのか? 気になって仕方がないんだって話をどこかでしたら、それを知った友部正人さんが宮沢さんに直接メールで回答してくれたんだって。
・
という話を、NHKアナウンサーの道谷眞平さんが読み上げた。じつは、宮沢さんに電話をつないで直接話を伺う段取りだったのだが、番組から電話をすると「留守電設定」になっていて、電話出演のことを宮沢さんはどうもすっかり忘れてしまっていたようなのだ。
このドタキャン騒ぎに、さすがのなぎら健壱さんも怒ってましたよ。当日の夜、宮沢さんはツイッターで以下のように言い分け。
翌週、5月8日(月)の『すっぴん!』は、あまり悪びれるでも、ひたすら恐縮するでもなく、さらっと終わってしまったようだ。
・
■なぎら健壱さんのラジオで、友部正人の「あいてるドアから失礼しますよ」が流れたあと、出演していたシンガーの辻香織さんが、「私、友部さんが『たま』と共演したCD『けらいのひとりもいない王様』に収録されている『この曲』が大好きで、何度も聴きました」って言っているのを聴いて「おっ!?」と思った。
じつはぼくも「このCD」を最近中古で入手して、よく聴いていたのだよ。ここでもまた、不思議なシンクロニシティ。4月26日の午後松本へ行って「ほんやらどお」で中古CDを物色していたら、店番のバイトの男子学生さんが店内BGM用に「このCD」をかけた。1曲目「夢のカリフォルニア」。
スピーカーから流れてきた友部正人の唄声に「おおっ!」と思った。2枚目のレコード『にんじん』に収録されている「この曲」が大好きなんだ。でも、このCDは初見。学生さんに「これ、売り物ですか?」って訊いたら、彼個人のCDで売り物じゃないとのこと。残念。でもどうしても欲しくなって、ネットで見つけて購入したのでした。
・
■ところで、この曲の主人公が部屋に入ってくるのか、それとも出て行くのか? 宮沢さんは結局、月曜日のラジオでは教えてくれなかったようだ。



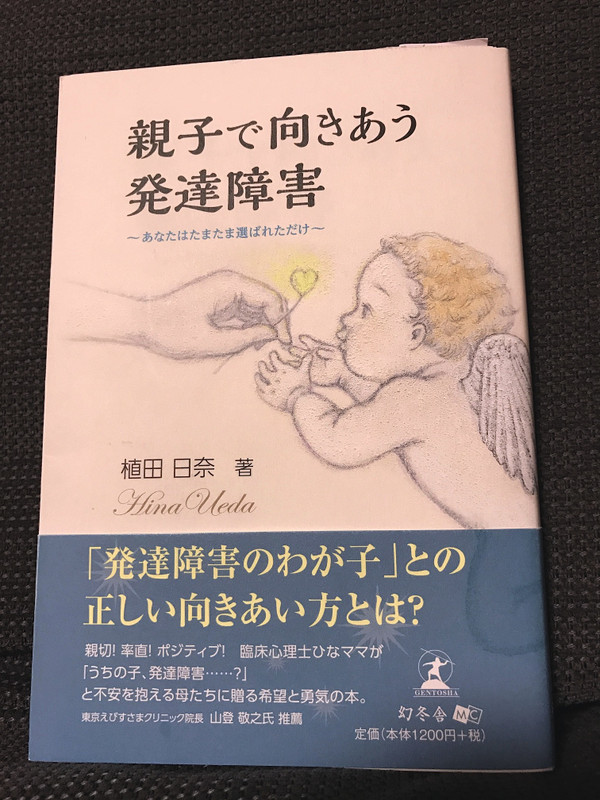
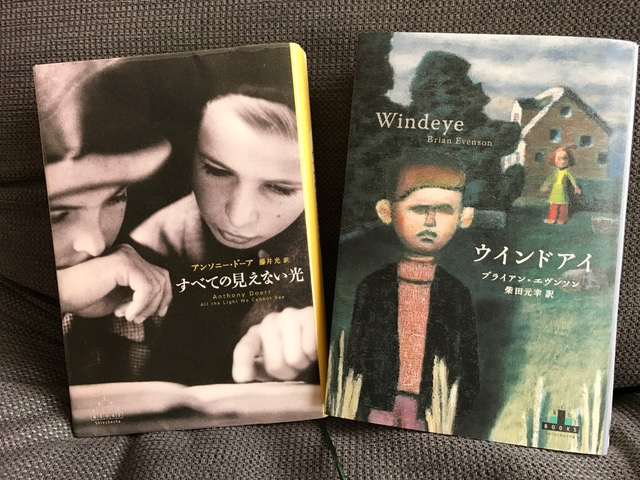
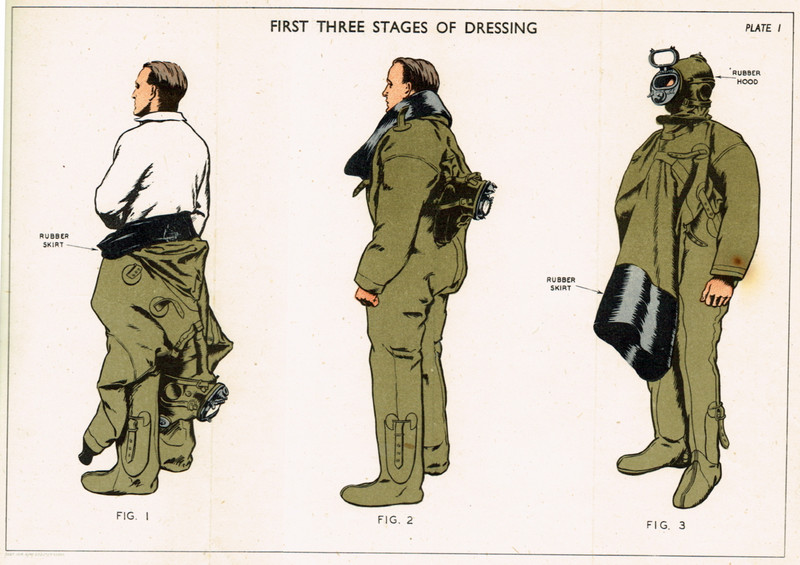





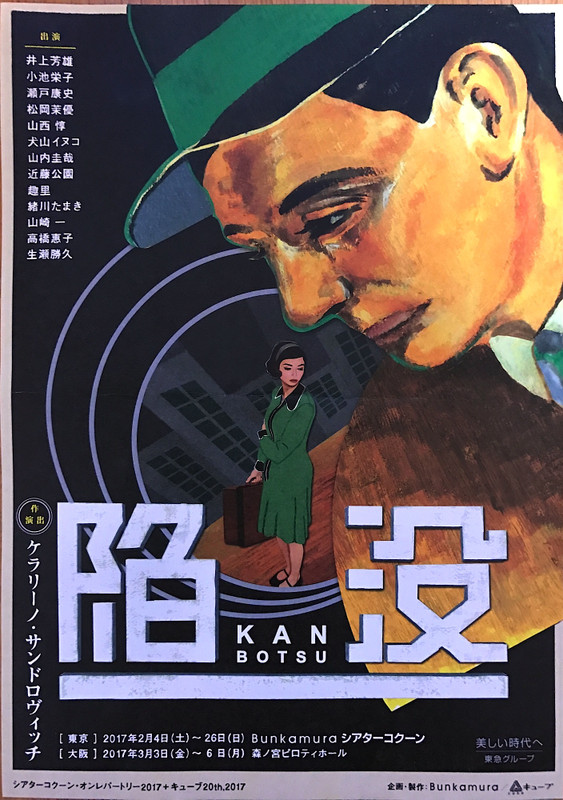
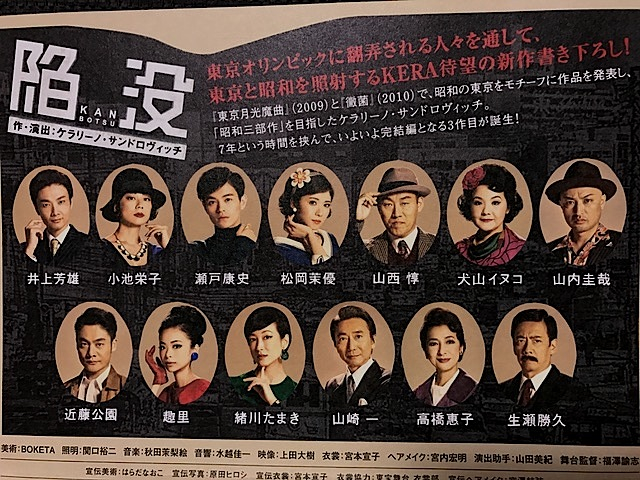

最近のコメント