『コルトレーン ジャズの殉教者』藤岡靖洋(岩波新書)
■本は薄いのに、内容はメチャクチャ濃い。
著者は、大阪の老舗呉服店の旦那はん。でも、趣味とか道楽とかの時限を超越している人で、世界的に有名なジョン・コルトレーン研究家なのだった。著書は、この岩波新書が3冊目で、初の日本語で書かれた本だという。と言うことは、前の2冊は英語で書かれたコルトレーンの本なのだそうだ。凄いな。
この本の中で、ぼくが一番に注目したのは p115 に載っている「アンダーグラウンド・レイルロード」という曲に関する記載だ。

■この曲は『アフリカ/ブラス Vol.2』に収録されていて、ぼくがジャズを聴き始めてまだ間もない頃、すごく気に入ってさんざん聴いた覚えがある。このLPジャケットにも見覚えがあったので、書庫のLP棚を探したが見つからない。もしかして所有してなかったのか? おかしいなぁ。で、ふと気がついたのだが、たぶんあのレコードは、ぼくが大学1年生だった時に長兄から借りた10数枚のジャズレコードの中の1枚だったに違いない。
だから、いまは手元にないし、どんな曲だったかすっかり忘れてしまった。しかも、残念なことに iTunes Store では取り扱っていない。仕方なく、amazonで輸入盤を注文することにした。ぜひ、もう一度じっくり聴いてみたい。まてよ? YouTube にならあるかもしれない。そう思って探したら、あったあった。そうそう、この曲だ。なんとまぁ、自信に満ち満ちた力強い演奏なんだ! ほんと、カッコイイなあ。

YouTube: John Coltrane - Song Of The Underground Railroad
いずれにしても、この本の一番の読みどころは「アンダーグラウンド・レイルロード」や「ダカール」「バイーヤ」「バカイ」「アラバマ」とタイトルされた曲の本当の意味が書かれている、第3章「飛翔」その2「静かなる抵抗」(p108〜p126)にあると思う。「音楽が世界を変える」と信じて、最後の最後まで力の限り演奏し続けたコルトレーンだが、その死から41年後になって、アメリカ初の黒人大統領が誕生することになるとは、さすがの彼でも想いもよらなかっただろうなぁ。
あと、この本を読んで面白かったことを、思いつくままに列挙すると、
・見たことのない珍しい写真や新事実が満載されている。
・南部で黒人教会の名高い牧師であった祖父からさんざん聴かされた黒人奴隷の話。
・信じられないくらい超過密な来日公演スケジュール。
・同郷の友を何よりも大切にするジャズマンたち。
・「ジャイアント・ステップス」にも収録された、カズン・メアリーのこと。
・戦後すぐ、ハワイ真珠湾で海軍の兵役につていたこと。
・その時、任務をサボって収録されたレコードを聴いたマイルズ・デイヴィスが
コルトレーンをメンバーに招聘したこと。
・コルトレーンという名字は、アメリカでもすごく珍しい姓。
・母親が12回の分割払いで、息子のために中古のアルトサックスを買ってくれたこと。
・良き友であり、良きライバルであった、ソニー・ロリンズのこと。
・彼に白人の愛人がいたこと。その彼女が日記を残していたこと。
・アリス・コルトレーンのこと。
・名盤『至上の愛』誕生秘話。
・コルトレーン「でも、どうやって(演奏を)止めたらいいのか、わからないんだ」
マイルズ 「サックスを口から離せばいいだけだ!」
・それから、巻末に収録された「当時のニューヨーク地図」。
当時のジャズクラブの場所や、ジャズメンのアパートの位置が記入されていて、
これは楽しかったな。そのうち、タイムマシンが実用化された時には、すっごく
役立つ地図になると思うよ。
そしたら僕は、1961年7月のドルフィー&ブッカー・リトル双頭コンボを見に、まずは
「ファイブ・スポット」へ行くな、やっぱし。


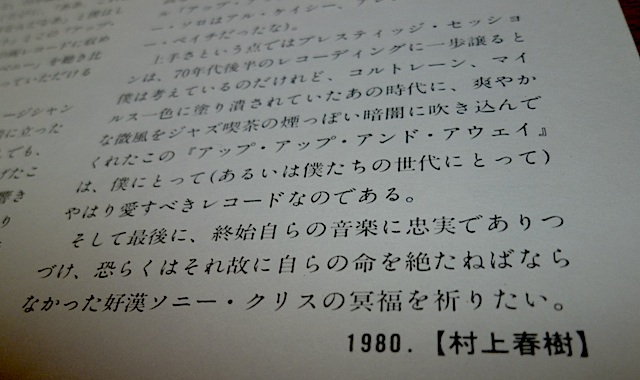



最近のコメント