■伊那市のNPO法人「こどもネットいな」が年に一度出している『ひとなる』という小冊子のために書いた文章なのだが、途中で書き進めなくなってしまい、自分でボツにしてしまったものです。でも、せっかく書いたのでここにアップしておくことにしました。お目汚し失礼致します。
小説に登場する「父親の子育て」
北原こどもクリニック 北原文徳
平成10年4月23日に伊那市境区で小児科医院を開業して、今年で15年になります。それにしても早いものです。あっという間でした。15年という年月が正直信じられません。ただ、開業時にまだ妻のお腹の中にいた次男がいま中学2年生で、当時1歳だった長男も高校1年生となり、今にも父親の背丈を追い越す勢いなのだから、子供たちの成長が、この15年の確かな証しなのだなあと、しみじみ感じています。
本当に、子供はあれよあれよと大きくなります。6年前の夏、当時8月の終わりに鳩吹公園で毎年開催されていた「まほらいな地球元気村」に何回か親子4人で参加し、その機関誌『元気村通信』(2006年秋号 vol.42)に「父親の子育て」に関して文章を載せてもらったことがありました。個人的にすごく思い入れのある文章なので、すみませんが以下に再録させて頂きます。
ぼくの父は、映画『東京物語』で山村聰が演じていたような町医者だった。夜中でも、日曜日でも、急患があれば年中無休で往診に出かけた。それが当たり前の時代だったのだ。だから、年の離れた二人の兄たちは、父親に何処かに連れて行ってもらった記憶があまりないという。でも、三男のぼくは違った。父は日曜日になると、ぼくを車に乗せてあちこちよく出かけたのだ。11年前に亡くなった父にその真意を確かめることはできないが、自分が父親になってみると、当時の父の気持ちが何となく判るような気がする。
子供はあれよあれよと大きくなってゆく。長男は10歳になった。小2の次男もこの半年でぐんと背が伸びた。あと10年もしないうちに、二人ともわが家から巣立っていってしまう。一つ屋根の下、親子水入らずでいっしょに暮らす期間というのは案外短いのだ。ぼくの父はそのことに気が付いたに違いない。
父が死んだ翌年の夏、ぼくの長男は生まれた。父親になったぼくは、赤ん坊を抱っこしながら、親子でキャッチボールをしたり、本気でプロレスごっこに興じる姿を思い浮かべた。さらには、渓流に二人して黙って釣り糸を垂れ、夜にはテント横の焚き火を囲んで、少し日焼けした息子の顔を見ながら「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい」そう思っている自分をイメージした。教条的な父親にだけはなりたくないな、そう思っていた。大好きな椎名誠さんの『岳物語』に多分に影響されていたからだ。
あれから10年が経つが、現実は理想通りにはゆかない。4の字固めですら息子にかけられないし、コントロールの悪いぼくの投球は、息子のグローブの1m上空を越えて行く。先日の尾白川キャンプでは、満足にテントも設営できなかった。格好悪い父親だった。次男は一生懸命、彼なりに慰めてくれた。思春期の手前にさしかかった長男は、ちょっと冷ややかな目でぼくを見上げた。彼が父親を越えて行く日も近いのかもしれない。『十五少年漂流記』を息子が寝る前に読み聞かせしながら、ぼくはふとそう感じた。
この夏、『川の名前』川端裕人(ハヤカワ文庫)を読み終わり、カヤックで川下りする話を思い出し、久しぶりに『続岳物語』を手に取った。やはりこの本は傑作だ。既に椎名私小説の最新作『かえっていく場所』を読んでいただけに、しみじみしてしまう。そうだ、俺は野田知佑さんを目指せばよいのだ。伊那のパパ'sにはうちの息子たちの他に元気のいい男の子が5人いる。彼らの「モ・ノンクル(僕のおじさん)」になろう! ちょっと不良な小父さんにね。
いま読むと、多分にアウトドアを意識した文章が可笑しいですが、あの時に西町の「アウトドアショップK」で購入した小川のテントも、長男が中学に入学した後は部活が忙しくて、結局一度も使われることなく裏のイナバ物置に収納されたままです。中学生になると、父親とはもう遊んでくれません。淋しいものですね。

『続 岳物語』椎名誠(集英社文庫)も、椎名誠氏の長男「岳君」の中学入学式当日の場面で終わっています。愛読者としては『続々岳物語』を読んでみたかったのですが、さすがの椎名氏も、思春期の嵐真っ直中の中学生時代の「岳君」を小説の題材にすることはできなかったようです。やはり、父と子の蜜月時代は小学校までなのですね。
この小説の中で僕が特に好きなのは、巻頭の「あかるい春です」と中盤の「チャンピオン・ベルト」。地の果てパタゴニアで椎名さんが息子のために手作りしたチャンピオン・ベルトを巡って、父と子で壮絶なプロレスの死闘が繰り広げられるのです。この部分、最初に読んだ時、ものすごくうらやましかった。
【図1】『チリ最南端の町、プンタアレナスの金物屋「アギラ」で材料を調達した椎名誠氏自家製のチャンピオン・ベルト 』
岳君は10歳になり、小学校高学年を通して、野田知祐氏から釣りやカヌーの手ほどきを受けます。野田さんは、この本の解説で「いい父親であるのは難しいが、いいおじさんであるのはやさしい」と書いていて、父と子の縦の関係よりも、小父と子の「斜めの関係」が案外重要であることを示唆しています。

父親と息子が登場する小説で印象的なのが『川の名前』川端裕人(ハヤカワ文庫)です。この作者は少年が主人公の話が本当に上手い。NHKでアニメにもなった『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)もそう。
『川の名前』は、東京都内に住む夏休み前の小学生の主人公が、教室からふと窓の外を眺めると、多摩川支流のその川に「小さな恐竜」を一瞬見たような気がした。そして……というお話。これ面白いです。一気に読めます。川端さんの小説はどれもいいですが、ぼくが一番好きなのは『手のひらの中の宇宙』(角川文庫)。やはり父親と息子の物語ですが、時間と空間、生命と死といった深淵で壮大な世界を垣間見せてくれる不思議な小説です。
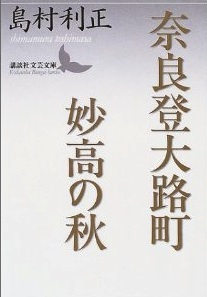 いま、ふと思い出した「父と息子」の短篇小説がありました。それは、昨年生誕100年を迎えた高遠町出身の小説家、島村利正の私小説『妙高の秋』です。これもいい。すごくいい。江戸末期、高遠城下で御用商人を務めた老舗海産物商の長男として生まれた島村氏は、文学への道をどうしても捨てきれず、父親の期待を裏切って家出のようにして高遠の家を捨てるのです。まだ14歳の3月初めのことでした。
いま、ふと思い出した「父と息子」の短篇小説がありました。それは、昨年生誕100年を迎えた高遠町出身の小説家、島村利正の私小説『妙高の秋』です。これもいい。すごくいい。江戸末期、高遠城下で御用商人を務めた老舗海産物商の長男として生まれた島村氏は、文学への道をどうしても捨てきれず、父親の期待を裏切って家出のようにして高遠の家を捨てるのです。まだ14歳の3月初めのことでした。
そうした父と子の確執と和解を綴っていて、淡々とした文章でありながら、著者の胸の裡に去来する様々な思いを、読者は否応なく体感させられます。『仙酔島』『庭の千草』も、決して幸せではなかった祖母や叔母の人生を「あれでいいのだ」と肯定してあげる著者の優しさが心に沁みます。
伊坂幸太郎『ゴールデンスランバー』(新潮文庫)は映画版もよかったですね。ある日突然、首相暗殺の犯人に仕立て上げられた堺雅人が仙台の街中を逃げ回ります。彼の実家に押し寄せたTVレポーターに向かって、父親の伊東四朗が言い放った言葉に泣けました。父親はこうでなきゃいけない。
「おまえ、雅春のことをどれだけ知ってるんだ?言えよ。どれだけ詳しいんだよ。信じたい気持ちは分かる? おまえに分かるのか? いいか、俺は信じたいんじゃない。 知ってんだよ。俺は知ってんだ。あいつは犯人じゃない。雅春、ちゃっちゃと逃げろ!」
 小説ではありませんが、向田邦子『父の詫び状』(文春文庫)を読むと、明治生まれの頑固な父親像が、娘の目を通して様々なエピソードと共に印象的に描かれていて実に読み応えがあります。向田さんの文章は、読んでいて読者の五感に直接訴えてきます。食べ物の美味しそうなにおい、写真館で担任の先生の手が彼女の肩に触れた感触など、視覚聴覚以外の感覚(嗅覚、触覚、味覚など)もリアルに刺激されるのです。
小説ではありませんが、向田邦子『父の詫び状』(文春文庫)を読むと、明治生まれの頑固な父親像が、娘の目を通して様々なエピソードと共に印象的に描かれていて実に読み応えがあります。向田さんの文章は、読んでいて読者の五感に直接訴えてきます。食べ物の美味しそうなにおい、写真館で担任の先生の手が彼女の肩に触れた感触など、視覚聴覚以外の感覚(嗅覚、触覚、味覚など)もリアルに刺激されるのです。
戦前の一家の家長として暴君のように威張って君臨した父親の人生。私生児として生まれ、親戚からは村八分にあいながら、母親の賃仕事で大きくなった惨めな少年時代。高等小学校卒で給仕として保険会社(第一徴兵保険)に就職。しかしその後、誰の引き立てもなしに会社始まって以来といわれる昇進を果たし、保険会社の支店長にまで登りつめるのです。以後、宇都宮→東京→高松→鹿児島→東京→仙台と各支店を家族と共に転勤してまわります。
中でも、鹿児島時代のエピソードが出色で、「ねずみ花火」「記念写真」「細長い海」あたりが実にすばらしい。向田邦子は、9〜10歳頃の前思春期時代のことを実に鮮明に記憶していてほんと驚いてしまいます。
せっかちで、空威張りで、それでいて涙もろく子供っぽいところもある父親のことを、向田邦子さんは一見すごく鬱陶しく嫌っているようでいて、その実ほんとうは愛おしく思っているのですね。
そして、彼女の振るまいの其処此処に父親の影を感じる自分がいる。父と娘。じつはよく似た二人だったのです。(未完)
■追記■
<取り上げる予定だった本>
・『なずな』堀江敏幸(集英社)
・『きつねのつき』北野勇作(河出書房新社)
・『13日で「名文」を書けるようになる方法』高橋源一郎(朝日新聞出版)




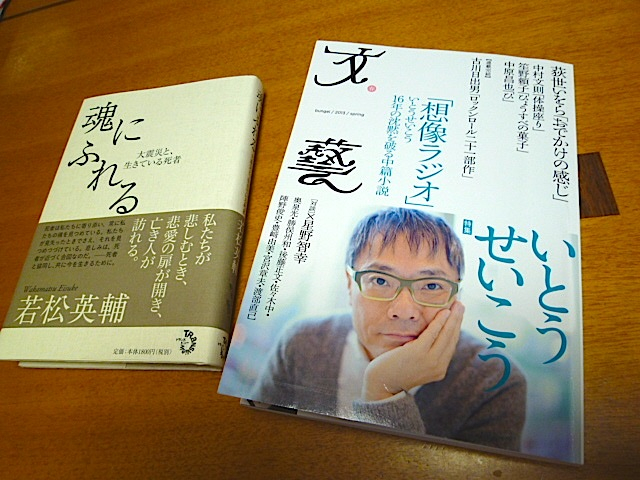





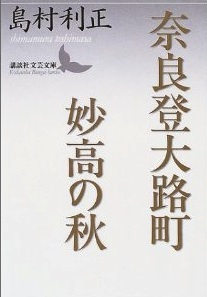 いま、ふと思い出した「父と息子」の短篇小説がありました。それは、昨年生誕
いま、ふと思い出した「父と息子」の短篇小説がありました。それは、昨年生誕 小説ではありませんが、向田邦子『父の詫び状』(文春文庫)を読むと、明治生まれの頑固な父親像が、娘の目を通して様々なエピソードと共に印象的に描かれていて実に読み応えがあります。向田さんの文章は、読んでいて読者の五感に直接訴えてきます。食べ物の美味しそうなにおい、写真館で担任の先生の手が彼女の肩に触れた感触など、視覚聴覚以外の感覚(嗅覚、触覚、味覚など)もリアルに刺激されるのです。
小説ではありませんが、向田邦子『父の詫び状』(文春文庫)を読むと、明治生まれの頑固な父親像が、娘の目を通して様々なエピソードと共に印象的に描かれていて実に読み応えがあります。向田さんの文章は、読んでいて読者の五感に直接訴えてきます。食べ物の美味しそうなにおい、写真館で担任の先生の手が彼女の肩に触れた感触など、視覚聴覚以外の感覚(嗅覚、触覚、味覚など)もリアルに刺激されるのです。
最近のコメント