■テルメで6km 走った後にフロント前のロビーで、8月14日付「日本経済新聞・日曜版」最終面に載っていた、元大阪大学総長、鷲田清一氏の『閉ざした口のその向こうに』を読んだ。さすが、しみじみ深く感じ入る文章だった。
ネット上でも、日経の無料会員に登録すれば、読むことができるが、以下、一部(というか、そのほとんどを)転載する。
・
お盆前後の半日、両家の墓に参る。若い頃は墓参りは両親にまかせていたが、いまはわたしたち夫婦以外にその務めをする者がないから、空いている日を見つけ墓所を訪ねるのが、この季節の習いになっている。京都では十六日に「送り火」という、街をあげての精霊送りの行事もあるから、どこからともなく線香の匂いが漂ってくる。
・
若い頃は逆だった。なぜこの日に、そしてこの日にかぎって厳粛な気持ちになるのか。そこに、大人たちのうさんくささを嗅ぎつけ、あえてその日を特別な日にしないぞと、家族の墓参りには同行しなかった。できるだけ普段どおりを装うようにしていた。これが十代の頃の、わたしなりの「大人」たちへの不同意のかたちであった。
・
特別な日にあらたまって何かに思いをいたす。かわりに普段は平気でそれを忘れている。普段は弔いの思いもない者がその日だけ手を合わせる、線香を焚(た)く、そんなふうに形だけ整えるのを、偽善と感じたのだろう。「あらたまる」というのは、日々の思いがあってこその、その思いの凝集であるはずだと。(中略)
・
いつの頃からか(中略)ときどきふと、思いもよらないものに目を止めるようになった。長年使ってきた艶のない食器にふと目を落としたり、通りなれた道を歩きながらふとこれを見るのも最後かもとしみじみ眺め入ったり、ふと見かけた子の行く末が気になったり、そして何より、とうにいない父や母、祖父、祖母のかつての姿を思い起こしたり。(中略)
・
何年くらい前のことだろう、ある日ふと、食卓にあっても家族と目を合わせることのほとんどなかった父の姿が思い浮かんだ。細かな擦り傷だらけ、ところどころかすかに鈍い輝きを放つだけのあの食器のように。
・
父とこころを割って話すことはついに最後までなかった。ずっとそう思ってきた。しかしほんとうは話していたのかもしれない。口から漏れかけた言葉にただこちらが気づかなかっただけのことかもしれない。「かたり」が「語る」であるとともに「騙(かた)る」でもあるように、記憶もまた、それと気づくことなく体の奥に刻まれていることもあれば、後からキレイな話につくり変えられていることもある。
・
わたしには戦争の記憶はもちろんないが、父をめぐる記憶も終戦の数年のちから始まる。父については口下手というか口が回らないという印象がずっとあった。口数の少ない父がことさら寡黙になるのは、きまって戦地の話になるときだった。何を訊(き)いてもなしのつぶて。ちらっと「何でそんなこと訊くんや」という顔をするばかりだった。かろうじて聞き出せたのは、子どもの頃の事故で片眼の視力を失っていたので、前線の後ろ、衛生兵に配属されたということだけ。祖父が空襲の話を饒舌(じょうぜつ)にくりかえすのと対照的だった。
同級生に訊くと、よその家でも親父というのはそんなものだったらしく、それ以上詮索することもなく月日は過ぎた。
・
その沈黙を世代として受けとめなおす必要があると、このところ思いはじめている。声高の戦争語りには、子どもなりに反撥(はんぱつ)していた。が、その勢いで、言葉が滞るというかたちでの父たちの戦争の語りにも同時に耳を塞いでいたのだと思う。けれどもとさらに思う。「わたしたち」は太平洋戦争を体験していないけれども、その体験者の失語にふれた最後の世代に属する。その人たちが断ち切ろうにも断ち切れなかったもの、少なくともその残照には「わたしたち」はふれていたはずなのだ。皮膚に細かいひっかき傷として残っているそれらを語りつぐ務めがわたしたちにはあるのではないか。
□ □ □
父は死ぬまで仏壇だけは疎(おろそ)かにしなかった。生まれてすぐに母を亡くし、それからずっと親戚の寺で預かってもらっていたというから(この話も父ではなく親戚筋から聞いた)、理由はそこにあるかもしれないが、そのときだけは戦地で逝った戦友のことを密(ひそ)かに思っていたのかもしれない。あるいは、消えるような声でたどたどしくしかお経を読めなかったのも、たとえお経であっても、走る言葉は信用しないということがあったのかもしれない。いずれもすべて霧の向こうにある。
・
父(たち)は何を拒んでいたのか。何を断念したのか。何がまだ済んでいなかったのか。
・
足腰が弱くなって、ついでに「じぶん」というものまで痩せ細ってきて、何を見ていてもその光景に思いもかけずこの問いが重なることが増えた。父の代から引き継いだ盆の墓参りの道すがら、服にしみつく線香の匂いも昔とはかすかに違ってきている。
『閉ざした口のその向こうに』鷲田清一(8月14日付「日本経済新聞・日曜版」最終面より)
・
・
■「『わたしたち』は太平洋戦争を体験していないけれども、その体験者の失語にふれた最後の世代に属する。」という言葉が重要だ。『わたしたち』とは、どこまでの世代が含まれるのか?
・
鷲田先生は、1949年生まれだ。以前ブログに書いた「同じ年生まれの人が気になるのだ」で調べてみると、村上春樹が同じ 1949年の早生まれだ。ちなみに、後で触れる予定の、辺見庸氏は 1944年生まれだった。
・
■ぼくの父は、大正8年の生まれで、昭和19年、慈恵医大を卒業し陸軍軍医学校に行った。戦地へ派遣されることはなかったが、3月10日の東京大空襲の惨劇を、軍医として目の当たりにしたという。
昭和20年10月。氷川丸に乗ってラバウルへ患者さんたちを引き取りに行くべく横浜港で待機中に、故郷の高遠町で外科医院を開業していた祖父危篤の電報を受け帰郷。翌年、亡くなった祖父の跡を継ぎ、父は27歳で内科医院を開業した。本当は、大学に戻って尊敬する教授がいた産婦人科学教室に入局する希望だったのだが、叶わなかった。
ぼくの長兄も、1949年(昭和24年)の早生まれだ。だから、鷲田先生や村上春樹氏の父親も、ぼくの父と同世代に違いない。
・
■村上春樹氏の父親も、中国大陸に従軍している。しかも、モンゴル・ソ連国境に接する「ノモンハン」だった。村上氏は、エルサレム賞受賞のあいさつ「壁と卵」の中で、彼の父親に触れている。以下抜粋。
・
私の父は昨年の夏に90歳で亡くなりました。彼は引退した教師であり、パートタイムの仏教の僧侶でもありました。大学院在学中に徴兵され、中国大陸の戦闘に参加しました。私が子供の頃、彼は毎朝、朝食をとるまえに、仏壇に向かって長く深い祈りを捧げておりました。
一度父に訊いたことがあります。何のために祈っているのかと。「戦地で死んでいった人々のためだ」と彼は答えました。味方と敵の区別なく、そこで命を落とした人々のために祈っているのだと。父が祈っている姿を後ろから見ていると、そこには常に死の影が漂っているように、私には感じられました。
父は亡くなり、その記憶も ---- それがどんな記憶であったのか私にはわからないままに ---- 消えてしまいました。しかしそこにあった死の気配は、まだ私の記憶の中に残っています。それは私が父から引き継いだ数少ない、しかし大事なものごとのひとつです。
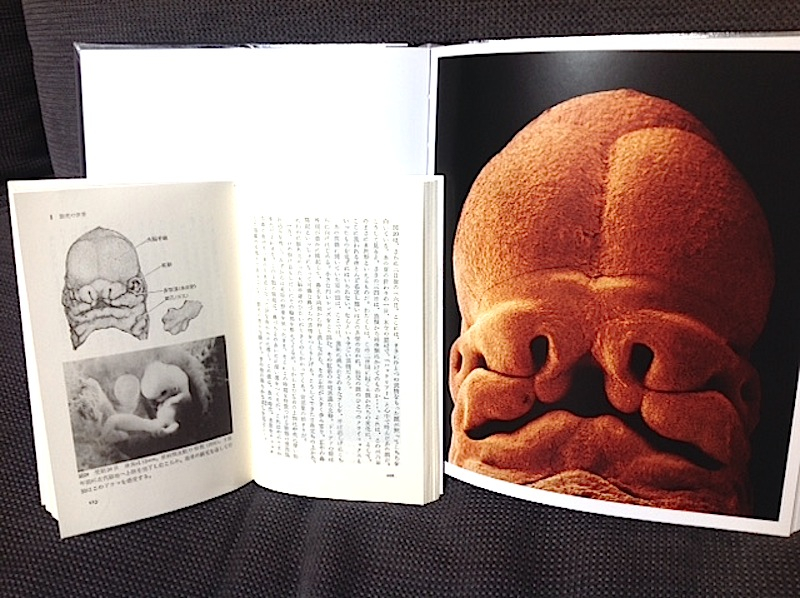

最近のコメント