太田省吾『舞台の水』(五柳書院)つづき
■昨日のつづき。『舞台の水』太田省吾(五柳書院)より、76ページ「演劇とイベント」
○
企画の時代で、演劇の世界も企画の目を意識しないとやっていけなくなっている。(中略)
だが、と私は演劇について思う。演劇もイベントにちがいないが、所謂イベントとどこかはっきり異なるところのあるものではないかと思うのだ。演劇は、それがどこかというところを見出さなくてはならない。なんだか、イベントと演劇の区別がつきづらくなっている。
「痛み、怖れ、ためらい、はじらい、おののきの基本要素がなければ、詩は生まれない」。リルケの言葉だが、私はこの「詩」を「演劇」と置きかえ、「どこか」とは結局のところここらあたりではないかと思っている。なんだと思われるかもしれないが、このリルケの言葉は、喜怒哀楽を除外しているところを注目しなければならない。
喜怒哀楽を除外するとは、わかりやすく通じやすいところから詩は生まれないと考えることであり、詩を生むのは自分にとっても把えにくいところだとすることである。
企画の目では、これがまどろっこしい。こういうところを棄てて進もうとする。この「詩」を「演劇」と読みかえれば、「演劇」を棄て、もっと通じやすいところ、いわば喜怒哀楽へ行こうとする。その方向をイベントというのではないか。
■
■
■p26〜p28 「<反復>と美」より
演劇の稽古にはくりかえしが欠かせない。ほんの小さな一つの行動や台詞を半日くりかえしているなどということもよくあることだ。
そんなとき、何をしているかといえば、多くの場合、たとえばコップに手をのばしコップを取って水を飲むという行動があるとすると、それが最も適確だと思われるやり方をみつけるため、あるいはそれが演技で充分表現できるようにするためである。(中略)
しかし、私はこのくりかえしをもう少し別の目で見、気づいたことがあった。私には、それは一つの発見のように思えたのだった。
適確さとは、その人物の設定やその人物が置かれている状況とその行動との関係で見出されていくものだが、そのときには、そんな関係をなしに、ただただその行動をくりかえしてみていたのだった。
いわば裸のくりかえしだった。コップを見、コップへ手をのばし、水を飲む。コップを見、コップへ手をのばし、水を飲む。コップを見、コップへ手をのばし、水を飲む……。
この反復の中で浮かびあがってくるものがあった。その動作が、いわば不定詞のように、つまり「人間がコップを見るということ」であり、「コップ(物)へ手をのばすということ」であり、「水を飲むということ」といったように際だって見えてくる。そして、その主語は個別性を越えていくように見えたのだった。
ある人物という主語、つまり<役>とは、ある住所氏名年齢職業性格、といった限定ををもち個別性をもつということだが、それらを失い、それらを越えていった。
それらの動作の主語、主体は、ある俳優の身体を通じてであるが<類>へ近づいていったように思えた。ある俳優の身体が、人類、人間と溶け合うように思い、それを、私は美しいと感じたのだった。
人間が物(コップ)を見るということ、人間が物に手をのばすということ、人間が水を飲むということ、ある一個の身体を通じて人間の動作をそんなふうに見ることのできるということ、そんなふうに見ることができる時間をもつことができるということは、演劇の大きな望みなのではないだろうか、そんなふうに思えた。自分の演劇への望みがそういうものだとわかったように思えたのだった。
私の劇のテンポは遅い。かなり遅い。その遅さは、言ってみればどのような動作も、この、反復を含んだものとするためであり、そうしなければ見ることのできない人間の美を見ようとしていることなのかもしれない。
■
■
■p24 「舞台の水」より
「ドラマとは、人生の退屈な部分を削除したものである」という根強い考えがあるが、私はかならずしもそう考えない。そして、それは私だけの考えではなく、現代の表現が徐々に見直している中心のところだと言ってよいのではないだろうか。
J・ケージは、サティの曲を「魅力的な退屈さ」と言い、サティに学んだことはこういうことだと述べている。
音は音であり、人間が人間であることをそのまま受け入れて、
秩序の観念とか感情表現とか、その他われわれが受け継いで
きた美学上の空論に対する幻想を捨てなければならない。
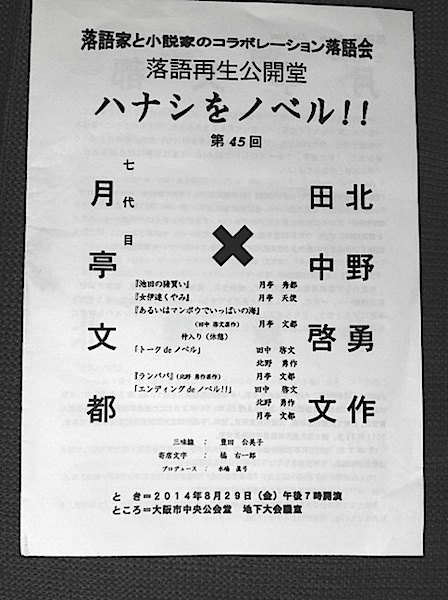

最近のコメント